ダイヤモンド・オンライン
ウェブサイトスポンサー企業(記事数上位10社)
掲載記事
全 1,485 件中 1,001 - 1,020 件を表示

安定収益、節税、承継中小企業オーナーの3つの悩みを解決する収益不動産活用を提案
中小企業の多くが厳しい経営に直面するなか、オーナー経営者の3つの悩みである安定収益源の確保、節税、事業承継を収益不動産活用で一気に解決することを提案するのが大和財託だ。代表取締役CEOの藤原正明氏に聞いた。

社内文書というナレッジをAIで抽出して共有
高度な自然言語(人間の言葉)処理技術を持つストックマークが提供する「Asales」(エーセールス)は、社内に蓄積された企画書や提案書から営業ノウハウを抽出する営業支援ツール。その活用方法と、実際に導入して成果を上げている事例を紹介する。

Web会議システムより演出効果が高く、視聴者の心に響くオンラインイベントの新潮流
新型コロナウイルスの感染拡大とともに、新商品発表会や記者発表会、入社式、社内表彰式、セミナーなど企業が催す社内外のイベントは自粛を余儀なくされている。Web会議システムを使って代替する動きもあるが、演出効果の高いリアルなイベントに比べると味気なく、主催する企業の思いや、商品・サービスの魅力が十分に伝え切れないのが実情だ。そこで注目したいのが、リアルを上回る臨場感や、活発な双方向コミュニケーションを実現するオンラインイベントの新サービス「WEBENT(ウィベント)」である。「WEBENT」では登壇者のスタジオ撮影を行うだけで、オンライン上でさまざまなステージ装飾、演出効果を設定可能。記憶に残るオンラインイベントを発信できる拡大画像表示 新型コロナ感染症を拡大させないため、いわゆる“3密”(密閉・密集・密接)のリスクが高いイベントの在り方を根本から見直す、新しいスタイルが求められている。もちろん、企業が主催するイベントも例外ではない。本来行うはずだった新商品発表会やセミナーなどを見送り、販売計画などを下方修正せざるを得ない企業も少なくない。 また、人材獲得のためのイベントが開催できないことも大きな問題だ。会社説明会をはじめとするリクルート目的のイベントは、学生に直接会って自社の魅力を伝える絶好の機会だが、それを自粛せざるを得ないとなると、ただでさえ少子化で人材確保が困難な中で、ますます人手不足に苦しむことになってしまう。 この他にも、企業が行う社内外向けイベントは新サービスの記者向け発表会、全社会議や優秀者表彰式、講演会、周年記念イベントなど多岐にわたる。中には、入社式や株主総会のように、開催しなくてはいけないイベントもあり、やむを得ずWeb会議システムなどを使い、代替しているのが実情だ。リアルでは実現できない舞台デザインや演出も自由自在ディーフレックス秋庭正明 代表取締役「Web会議システムでは、情報は共有できても、真に迫った“思い”を伝え、共感を得るのは容易ではありません。その意味で、リアルなイベントを代替する手段として物足りなさを感じている企業も少なくないようです」と語るのは、法人向けイベントの企画・制作会社であるディーフレックスの秋庭正明代表取締役である。 1988年設立のディーフレックスは、自動車メーカーや保険会社、製薬会社、食品メーカーなど、業種も事業規模もさまざまな企業からの依頼を受け、多様な社内外向けリアルイベントの企画・制作を行ってきた。 その中で、各企業から寄せられた「もっとリアルに近く、思いを伝える力を持ったオンラインイベントは開催できないか」というニーズが増えてきたことを受け、20年5月、最新のデジタルテクノロジーを融合させたリアルさながらのオンラインイベントを実現する新サービス「WEBENT」を開始した。 WEBENT開発責任者の深田博士氏は、「簡便さ、安全性はもちろん、より参加者の興味を引くため演出自由度にこだわっているのが大きな特徴です」と説明する。オンラインイベントではステージ装飾やセット構成、演出などが自由に設定できる拡大画像表示 WEBENTで開催するオンラインイベントへの参加者は、パソコンやタブレット端末、スマートフォンなどのあらゆるデバイスから、専用のソフトやアプリをダウンロードしなくても簡単に参加できる。リアルイベントのような人数制限もなく、数人から数千人規模まで、自由に参加人数を設定可能だ。 参加者にはユーザーIDとパスワードが付与され、ドメイン指定を使用した安全な配信を行うため、“招かざる客”が参加するリスクは排除される。そのため「記者発表会やアナリスト向けのIR説明会のように、秘匿性の高い情報を提供するイベントでも安心して開催できます」(秋庭代表取締役)。もちろん、誰でも参加できるオープンなイベントも開催できる。拡大画像表示 さらに大きな特徴として注目されるのが、リアルでは実現できないような空間まで思い通りに表現できる演出自由度である。 昨今の製品発表会では製品イメージの伝達やSNSでの話題作りに注力する企業が多い。WEBENTでは、オリジナル閲覧サイトの製作や視覚的に引き付けるバーチャルステージで企業の特色やブランド力を強くアピールできる。「物理的な制約に縛られることなくステージを大きく広げ、登壇者が指を鳴らすと背景の色が変わる、手をかざせばそこに商品が登場するといった、さまざまな演出が可能です。その意味では、リアルなイベントよりも訴求力が高いと言えるかもしれません」(深田氏)。

リモートワークでも大活躍!Slackが実現する新しい働き方とは?
社員が在宅勤務せざるを得ない状況に追い込まれるなか、多くの経営者や管理職は業務のあり方や労務管理の見直しを迫られ、「どうすれば社員同士の連携を保ち、業務を止めないようにできるのか」と悩んでいるのではないだろうか? 膨大なメールとチャットで情報量が多くなることによる情報の見落としや認識のすれ違いが円滑なチームワークを阻害し、業務のスピードを鈍らせていることは否めない。これを解決するには、単なる“チャット=会話”ツールの枠を超え、業務にかかわる人、データ、コミュニケーションを一元化できるメッセージプラットフォームの活用が有効だ。

一橋ビジネススクール・名和客員教授に聞くVUCAに挑む企業経営とCFOの新たな任務
経営環境がかつてないスピードで変化するデジタル化の時代にCFO(最高財務責任者)と財務部門に求められる役割とは何か。そして、その役割を遂行していくために不可欠な経営管理の基盤とはどのようなものだろうか。

パワハラ防止に効果的なアンガーマネジメント研修を提供する
今、怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニング、アンガーマネジメントをパワーハラスメント(以下、パワハラ)防止に取り入れる企業が増えている。日本アンガーマネジメント協会では、企業や自治体など、あらゆる組織で双方向型の研修(集合型・オンライン型)を実施、パワハラ防止を支援している。

eラーニング、通信教育、VRの三位一体でハラスメントの課題を解決する
「成長に寄り添う」をミッションに掲げ、研修やセミナーを通して企業や自治体の人材育成支援を行う日本能率協会マネジメントセンター。最近注目されるハラスメント研修では、eラーニング・通信教育・VR(バーチャル・リアリティー)を活用し効果的な支援を行っている。

ソフトバンク法人営業の事例に学ぶ業務量の削減と予実管理の精度向上
ソフトバンクで西日本全域の法人営業を統括する広域法人第二営業本部は、クラウド型BI(ビジネスインテリジェンス)ツールを活用し、業務量の削減と予算実績(予実)管理の大幅な精度向上という成果を上げている。

今からテレワークを始める企業は、最適な性能のPCとサービスをセットで選ぶべき
急なテレワーク導入が決定。しかし全社員が持ち出し可能なPCや、自宅に仕事で利用できるPCを持っているわけではない――。こんな場合、経営者やIT管理者はどんなPCをどのように用意すればいいのだろうか。情報システム部門などの専門部署や、PC・ネットに詳しい人が社内にいない場合は、何の機種を選ぶか決めるだけでも一苦労。「できるだけ安いものを」と値段重視で使いにくいPCを導入すると、社員の生産性を落とすことになる。コストを抑えながら、使いやすく、テレワークや、社員それぞれの業務に最適のPCを選択しなければならない。そんな企業にお勧めしたいのが、新しいPCの導入方法「Device as a Service(DaaS)」と、標準機はもちろんテレワークにも安心して使えるマイクロソフトの「Surface」である。

モビリティーと都市の未来像は、バーチャルツインによって明確に見えてくる
都市のデジタルトランスフォーメーション(DX)が注目される中で、モビリティーと都市開発が急接近している。3D(3次元)技術で自動車産業をはじめ、さまざまな業界の変革をサポートしてきたダッソー・システムズのギョーム・ジェロンドー氏と森脇明夫氏の2人に、モビリティーと都市の未来像と、その実現に必要な条件を聞いた。

データドリブン経営のソフトバンクはなぜクラウド型BIを大規模導入したのか
「データの裏付けがないプレゼンは受け付けない」。代表の孫正義氏がそう言い切るほど、徹底したデータ重視のビジネスを実践するソフトバンクグループ。通信サービス部門のソフトバンクも、その主義に基づき、データドリブン経営を推進している。そのソフトバンクの法人事業部門が、クラウド型BI(ビジネスインテリジェンス)ツール「Domo」(ドーモ)の大規模導入を決めた。その目的について、法人プロダクト&事業戦略本部事業戦略統括部の小松紀之統括部長と、同統括部営業支援部営業支援課の平之進担当課長に聞いた。

「店に出かけて買い物」が難しい今、小売店が目指すべき姿とは?
遠くの店に出かけて買い物をすることが難しくなっている昨今、ECサイトを利用する人が急増している。スマートフォンを手に、デジタルで情報収集することが当たり前な消費者が増えたこれからは、小売業はリアル店舗だけでなく、オンラインでの顧客接点を用いた活動へのシフトが求められる。今後、日本の小売業は、ビジネスをどのように再構築するべきだろうか。

RPAを導入した企業の多くがなぜ「期待外れ」に終わるのか
ビジネスの現場では、手作業による反復的なPC業務に毎日3時間以上が費やされており、従業員の41%がそうしたPC業務は退屈だと考えているーー。 これは、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)プラットフォームを提供するグローバル企業、オートメーション・エニウェアの調査結果だ。さらに同調査では、従業員の87%が、繰り返しの手作業を自動化するテクノロジーを導入してほしいと考えていることも分かっている。 一方経営者側は、働き方改革による残業の制限と有給休暇の取得義務の制度化、生産年齢人口の減少による採用難、ますます激化する競争環境といった経営課題を抱え、生産性向上が急務となっている。 こうした環境下でRPAの導入は必然であり、グローバルでは7割超の企業がすでに導入しているという。しかし多くの企業が「RPAを導入したのに期待したほど生産性が上がらない」と感じている。なぜだろうか。 RPA導入で企業が突き当たる「3つの壁」を整理し、それを乗り越えるためのポイントをまとめた。RPA導入の投資効果が得られないと悩んでいる企業は、ぜひ活用していただきたい。

受注、失注のプロセスを徹底分析すれば、営業組織の「勝ちパターン」が見える
営業活動をしていると、確実に受注できると考えていた案件を逃してしまうことがある。実はこれは、営業活動の経験が豊富なマネージャーから見ると当然のことを押さえていないからであることが多い。営業活動に関するコンサルティングを手掛けているTORIX株式会社の高橋浩一氏は、「接戦」となった商談を徹底的に分析していけば、「勝ちパターン」を作れると説く。

世界で活躍するマーケティングリーダーへの調査結果が明らかにする「企業のデジタル戦略のインサイト」
アドビとEconsultancyが共同で毎年行っている、調査レポート「Digital Trends」。グローバルでは10年目を迎え、本調査には、延べ7万5000人以上の各分野の世界的リーダーが参加している。 最新版となる「Digital Trends 2020年版」では、マーケティング、広告、eコマース、クリエイティブ、ITの各分野における企業や代理店のリーダー約1万3000人を対象にインタビュー。各企業の投資対象や優先順位、最大の課題を理解することを目的に、短期、中期的なマーケティング戦略における最も重要なトレンドに注目。10年という節目を迎える今回のレポートでは、「顧客体験の品質」に焦点を当て、顧客体験の最前線にいる企業をベンチマークとした比較検討を行った。 例えば、1.「デジタル格差が生み出す差異」では、先進企業は 顧客中心型の戦略に移行を進め 、そうでない企業に比べて、「2019年の主要な事業目標を大幅に上回る業績を上げることができた」と回答した割合が3倍にも達しており、先進企業が大きな成功を収めていることが調査結果から明らかになっている。 本調査は、1. デジタル格差が生み出す差異 「顧客体験が持つ真の価値」2. 2020年のマーケティング 「カスタマージャーニー向上のために」3. 企業文化が持つ力 「企業文化の重要性」4. プライバシーとデータ管理 「事前の計画が信頼性と透明性の確保につながる」5. 人工知能(AI) 「自動化による人的リソース不足の解消」といった5つのコンテンツで構成されており、企業のマーケティング担当者やデジタル担当者はもちろん、企業経営者が押さえるべきポイントを詳細にレポートしている。 ぜひこの機会に一読してほしい。
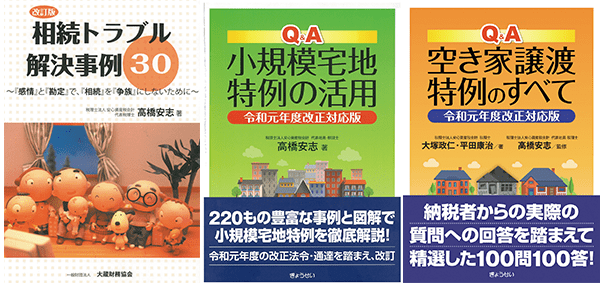
Business プロフェッショナル 相続編vol.1小規模宅地の減額特例にも精通!〝税理士が頼る〟資産税のエキスパート
税理士法人 安心資産税会計代表取締役社長 税理士 高橋安志1951年生まれ。83年税理士登録。相続税をはじめ資産税分野で豊富な実績を持ち、東京税理士会会員向けの講師も務める。「一見、法律や通達は、一分の隙もなく厳正厳格なように見えますがすべての事例に100%対応しているわけではありません。解釈によっては全く異なる評価が導き出される場合もある。要はいかに曖昧な部分を精緻に分析してクライアントの利益につなげるか、それこそがプロの腕の見せどころだと思うのです」と語るのは税理士法人安心資産税会計代表取締役社長の高橋安志税理士。実は、資産税の分野では〝業界の師〟と称され多くの税理士から頼りにされる〝プロ中のプロ〟としても知られている。その理由はとにかく徹底した仕事ぶりにある。 相続税をはじめとする資産税の節税は、資産の評価額を減らし控除額を増やすのが基本。特に土地評価で相続税額は大幅に変わってくる。まとまった土地を相続すると、評価次第では納税額に数千万円から数億円単位の開きが出ることもあるのだ。高橋代表はまず税制に関する法律や通達を歴史的変遷まで含めて調べ上げ、例外事項については過去の裁判の判例を参照し、さらに法令・通達を作成した財務省や国税当局の担当者本人に直接・間接的に取材することも厭わないという。まさにその手腕により、クライアントが満足する「結果」を獲得。資産家たちの厚い信頼を得ているのだ。

4月1日、改正健康増進法が全面施行。喫煙環境はどう変わる?
原則として屋内は禁煙になる改正健康増進法が2020年4月1日に全面施行された。しかし、喫煙者であっても、法改正の内容を十分に理解しておらず、「全ての飲食スペースが禁煙になる」などと誤解している人も少なくないようだ。たばこが吸える場所はどこで、吸えない場所はどこなのか。あらためて確認してみよう。

国内外の5つの先進事例に学ぶより速く、確実なデジタル変革
米国のプロスポーツチームから日本の農業生産法人まで、業種・業態の異なる5つの企業がデータドリブン経営に取り組み、大きな成果を挙げている事例を用意した。より速く、より確実にデジタル変革を実践する方法を学びとってほしい。

“脱炭素”社会の未来は、企業こそが鍵をにぎる。
「パリ協定」の実現とともに、2050年が大きな目標になる経済学者・東京大学名誉教授伊藤 元重中央環境審議会地球環境部会および長期低炭素ビジョン小委員会のメンバーを務める。 渡辺 最近、地球規模での気候の異常を実感なさる方も多いかと思いますが、その対策として「パリ協定」が結ばれ、日本は2030年度に2013年度比26%のCO2削減を目標としました。実現できるでしょうか。伊藤 非常に難しい問題で、とにかく長い時間がかかる。特に今は2050年の時点でどうなっているのか、今から何をすべきかを考えなければなりません。渡辺 なぜ2050年なのでしょう。伊藤 200年くらい前の産業革命の時点から比べて、2050年までに2度以上平均気温が上がると、かなり深刻な状況になりそうだとさまざまな研究データが示しています。例えばいろんな災害が起こり、生態系が壊れる。その長い時間軸の中で、同時に足元の問題をどう解決するか。もう少し目先のところで積み上げることも重要なのです。渡辺 子供や孫の代までですね。伊藤 方法論もたくさんある。だからビジョンを持つことは重要です。市場的手法が気候変動に対する大きなピジョンになる渡辺 先生のお考えになるビジョンとはどういうものですか。伊藤 一つは国が主導権を握り、目標を達成するための「規制」をする手法です。国民にもわかりやすく、国民の暮らしや産業界にも影響力や効果が大きい。それから、いわゆるエンジニアリング的な手法。経済産業省や経団連などが指標を作り、企業間で合意して実施するものです。しかしこの2つだけで、厳しい目標を達成できるかは不安です。渡辺 なるほど。他に考えられることはありますか。伊藤 期待できるのは市場的手法です。例えばESG(環境・社会・ガバナンス)投資、あるいは再生可能エネルギー100%で生産するとその企業の評価が上がるシステムなど、環境を考えている企業に資金が流れるようなイニシアチブに参画することが大切です。渡辺 世の中の人々の賛同を得られ、経済も潤うわけですね。伊藤 市場的手法は、大きなビジョンになると思いますよ。

企業の成長スパイラルを支援する人材育成プラットフォームを提供
人材育成・研修サービスに実績を持つ富士通ラーニングメディア。学習管理システム(LMS)である人材育成プラットフォーム「KnowledgeC@fe」をベースに、多彩な講義動画コンテンツを用意。次世代の学びの場を提供しながら、企業の成長スパイラルを強力に支援する。