日本マイクロソフト株式会社
スポンサード先
スポンサード記事
全 293 件中 181 - 200 件を表示

ウォルマート、ワークマンなどの成功事例に学ぶ あらゆる顧客接点を総動員し、実効力のあるブランドコミュニケーションを
新時代のオムニチャネルマーケティングを支える様々なテクノロジーやサービスが続々と登場している。本特集では、優れた特徴を持つ複数のソリューションを一堂に集め、動画で紹介する。

ニトリ、IKEAなどの成功事例を動画で学ぶ! 激変する流通小売業に最新テクノロジーが起こすパラダイムシフト
コロナ禍による変化により、流通小売業をとりまく課題は山積している。解決の ためには、デジタル変革が不可欠だ。ヤマトHD、ニトリ、IKEAなど多くの成功事 例をヒントに、解決策を探る。

いま私たちが直面する「働き方パラドックス」とは | 日本マイクロソフト | 東洋経済オンライン
米CDC(疫病対策予防センター)は、5月にワクチン接種完了者のマスク着用義務を解除した。“脱ステイホーム”が加速しており、オフィス勤務を復活させている企業も多い。しかし、完全にコロナ前の状態に戻ることは…

Teamsランチでリモートでもつながりを深める | 日本マイクロソフト | 東洋経済オンライン
「おかげさまで、『nonpi foodbox™』は多くの企業から引き合いをいただいています。とくに大手企業でのご利用が増えています」そう語るのは、ノンピ執行役員の綿貫貴大氏だ。同社は「食とコミュニケーション」を…

なぜ「Teams×アプリ」で生産性が上がるのか | 日本マイクロソフト | 東洋経済オンライン
コロナ禍となってから、オンライン会議やウェビナーは瞬く間に広がり、すでに定着している。対面での開催形態と比較して、時間や場所の制約がなくなるなど多くのメリットを享受しつつも、デメリットもそれなりに指…
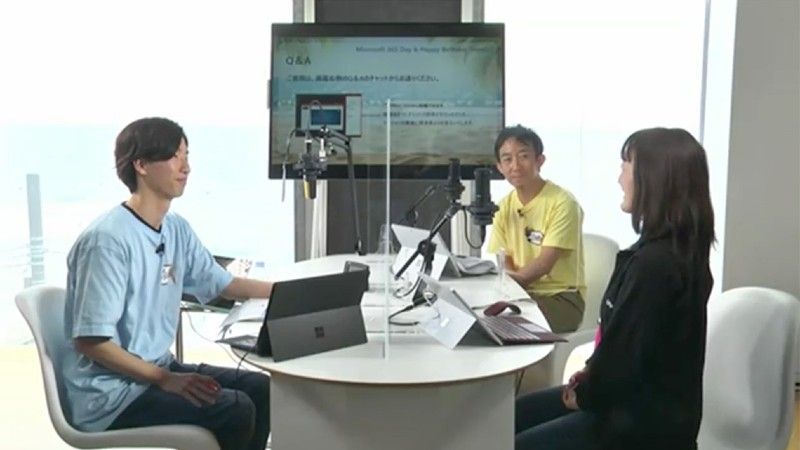
オンライン会議だけじゃないTeamsの魅力 | 日本マイクロソフト | 東洋経済オンライン
「当社の調査によれば、リモートワークにより生産性が高まったと回答した企業の割合は世界の平均値より日本のほうが高いという結果が出ています。一方で、従業員の孤立感や、疲労、ストレスは、他国に比べて高いで…

Mixed Realityから始まる産業革命 Microsoft HoloLens 2 の活用で“フロントラインワーカー”の生産性が飛躍的に向上! 複合現実が生み出す新たなビジネスチャンス 日経ビジネス電子版Special
IT と無縁だった現場業務に革新を起こす技術が注目されている。自分が見ている現実空間にホログラムを重ね合わせ、あたかもそこにモノがあるかのように確認・検証できる技術、「複合現実( Mixed Reality:MR )」だ。MRを活用すれば、離れた場所にいる現場担当者の視界と音声をリアルに共有しながらコミュニケーションがとれる。ここ数年、アプリケーションやデバイスが劇的に進化し、フロントラインワーカーの生産性が高まる手段として、様々な業界で導入が進む。今回、日本マイクロソフトでは、製造業、建設業向けに MR の先進事例や Microsoft HoloLens 2 の活用方法を解説するウェブセミナーを全4回にわたりオンラインで開催する。製造業、建設業で現場業務プロセスに課題を抱える企業担当者は必聴だ。

Mixed Realityから始まる産業革命 離島での医療格差を減らす診療システムを Mixed Reality と 3D カメラの融合で実現 日経ビジネス電子版Special
離島の数が日本一多い長崎県。その中心部にある長崎大学病院と離島にある長崎県五島中央病院(以下、五島中央病院)が、MR(複合現実)と 3D カメラを融合させたリウマチ遠隔診療システムを開発した。2つの病院をバーチャルにつなぎ、専門医による高度な診療を離島でも可能にする。患者の指の細かい皺までを 3D ホログラムで再現。遠隔地にいても、まるで患者が目の前にいるかのように診察できる。医療格差に苦しむ離島の医療を救う画期的な試みとして期待が集まっている。

Mixed Realityから始まる産業革命 ニューノーマルの時代を Mixed Reality で切り開く 日経ビジネス電子版Special
新型コロナウイルス、相次ぐ自然災害や異常気象、貿易摩擦など、今日のビジネス環境はかつてないほど不確実な状況にある。これを一過性のものと考えず、新たな常識「ニューノーマル」ととらえ、不安定な環境下でも事業を継続できる基盤作りがあらゆる企業に求められている。ニューノーマル時代に、Mixed Reality(MR)はどのような役割を果たしていくのだろうか。その使命やコンセプトについて、日本マイクロソフトへの取材を通して紐解いていく。

Mixed Realityから始まる産業革命 「AR匠RESIDENCE」の記者発表会をオンラインで開催 長谷工リフォームのマンション点検の実務に Mixed Reality を本格導入へ 日経ビジネス電子版Special
2020年7月6日、「AR匠RESIDENCE」の記者発表会が行われた。Mixed Reality(MR、複合現実)が、いよいよマンションの点検業務に本格的に導入される。人手不足や熟練技術者の減少を克服する新たな仕組みとして期待されるほか、将来的には、蓄積されたデータの活用や他業界への展開などが見込まれ、業界内外から注目を集めている。発表会は、新型コロナウイルスの影響を勘案し、日本マイクロソフトのテレビ会議システム「 Microsoft Teams 」による完全オンライン形式での開催となった。

Mixed Realityから始まる産業革命
今、現実世界にデジタル情報をシンクロさせる“ Mixed Reality ”が、あらゆるビジネスに革新をもたらそうとしている。その最前線に迫る。

Mixed Realityから始まる産業革命 武蔵精密工業が生産技術の分野にMRを活用 遠隔支援で海外の生産ラインを続々と立ち上げへ 日経ビジネス電子版Special
新型コロナウイルスの影響で、テレワークや遠隔コミュニケーションが普及しているが、海外に生産ラインを遠隔支援で立ち上げるとなると難易度は格段に高くなる。2020年6月、自動車部品を製造する武蔵精密工業が、Mixed Reality(MR)を活用し、遠隔支援だけでメキシコ合衆国に新たな生産ラインを立ち上げた。同社はこのノウハウを生かし、インドネシア共和国、ハンガリー、カナダへと、次々に同じ手法で生産ラインの構築を進めている。ものづくり大国日本のお家芸であり、何よりも現場・現物を重んじてきた生産技術の分野において、いよいよMRの活用が始まった。MRの活用は新たな常識(ニューノーマル)となるのか。

史上初!日本の伝統文化と Mixed Reality が融合 世界が日本文化に見るソフトパワーの本質とは -日経ビジネス電子版Special
米国時間の2020年2月27日(PST)、米ワシントン州シアトル市のベナロヤホールにて、 Mixed Reality (MR、複合現実)の活用に新たな一石を投じるイベント「 Ikebana X Technology 」が開催された。日本の伝統文化であるいけばなと、最先端テクノロジーのMRをライブで融合させるという、史上初の試みだ。海外のビジネスパーソンにとって、いけばなは単なる趣味ではない。決断力、チームワーク、独特の哲学、そして美意識など、日本の持つ独自のソフトパワーと認識され、ビジネスにも通じるインテリジェンスと捉えられている。パフォーマンスの様子をレポートするとともに、世界が日本文化に見ているソフトパワーとは何か、その本質に迫る。

Mixed Realityから始まる産業革命 長谷工がマンションの現場に Mixed Reality を導入 ファーストラインワーカーの生産性向上が本格化 日経ビジネス電子版Special
Mixed Reality(MR、複合現実)は、企業の最前線で活躍するファーストラインワーカーの生産性を向上させる立役者として期待されている。長谷工コーポレーションとアウトソーシングテクノロジーが共同開発した「AR匠RESIDENCE」は、まさにその期待を具現化する本格的アプリケーションだ。マンションの大規模修繕に伴う外壁検査の効率を飛躍的に高め、技術者の生産性向上と省人化を進める。MRで現場の仕事はどう変わるのか。その実際と効果についてレポートする。

Mixed Realityから始まる産業革命 製造、建設、医療、小売、あらゆる現場で精度と ROI を劇的に向上 Mixed Reality の活用で先行する欧米企業の事例を見る 日経ビジネス電子版Special
HoloLens 2 を活用し、数千社の先進的な企業が ROI の実績をつくりあげている。Mixed Reality の活用で先行する欧米企業の事例を動画で紹介する。

新しいビジネス様式の中心にある「Teams」 | 日本マイクロソフト | 東洋経済オンライン
武田 2020年4月に緊急事態宣言が発出され、急きょ在宅勤務に移行した企業がたくさんありました。宣言解除後に通常勤務に戻す企業があった一方で、取引先に訪問できずオンラインで会議をしたり、一部の社員や勤務…

ハイブリッドな働き方に適した会議室とは? | 日本マイクロソフト | 東洋経済オンライン
オンライン会議は、新型コロナが収束した後も必要とされるのだろうか?在宅勤務をはじめとするテレワークの需要は高く、総務省「令和2年版情報通信白書」によると、新型コロナ収束後もテレワークを継続したいと考…

イオン SM-DX Lab活動から考える 流通小売業DXの最適解 〜カギはデジタルの民主化〜 Labメンバーの知見編
小売業界のDX推進を目指して開催された「イオン SM-DX Lab」。未来のありたい姿から考える業界内外の連携可能性や、それを支える人材、組織作りについて議論が交わされた。先進企業の取り組みから見える、小売業界の次の一手とは。

イオン SM-DX Lab活動から考える 流通小売業DXの最適解 〜カギはデジタルの民主化〜
EC市場が拡大を続け、店舗の多様化も進み、既存の小売店は変革を求められている。イオンの食品SM(スーパーマーケット)部門でもDXの取り組みが進む。いち早くその重要性に気づき、取り組みを始めたイオン株式会社 SM・商品物流担当付 北村智宏氏。スタートから3年が過ぎて全社にDXの必要性が理解され始め、いよいよ実装段階に入る。北村氏と伴走する日本マイクロソフト インダストリーテクノロジーストラテジスト 岡田義史氏と共に話を聞いた。

つねに結果を出す「オンライン会議」の法則 | 日本マイクロソフト | 東洋経済オンライン
日本のビジネスシーンではとかく「無駄な会議」が多い印象がある。というのも、かつての日本では、会議が報告会になりがちで、本来の目的である「共創」や「意思決定」に直結しにくかったからだ。今では、そういっ…