ダイヤモンド・オンライン
ウェブサイトスポンサー企業(記事数上位10社)
掲載記事
全 1,485 件中 1,381 - 1,400 件を表示

「メイド・バイ・ジャパン」で日本農業を大転換
企業や業界の垣根を超えた「農業データの連携」こそが、日本が進めるべきIT農業の姿と主張する内閣官房 副政府CIOの神成淳司 慶應義塾大学環境情報学部准教授。熟練農家の暗黙知の継承に取り組むと共に、「データ連携による、多様な高付加価値化の追求」を後押しする農業プラットフォームの創設を進めているが、各社や各団体をまとめスタートラインに立たせるだけでも苦労の連続だったという。

“経験則に基づく名人芸”を次の世代の農家に継承
少子高齢化が進み、後継者不足が問題化している日本の農業。一方でIT化・AI化の大きな波は農業の世界にも押し寄せつつあり、欧州の大型農場では生産効率向上を目指した最新技術の導入が進んでいる。わが国において注目されているのは企業や業界の垣根を超えた“農業データ利活用”の動きだ。旗振り役を担う神成淳司 慶應義塾大学環境情報学部准教授が語った。

スマートハウスの普及で期待される新ビジネスとは
家庭のエネルギーを賢く管理する「スマートハウス」が本格的な普及期を迎えつつある。2020年には国内での市場規模が3兆5000億円になるという試算もある*。スマートハウスの普及に欠かせないのが「HEMS(ホームエネルギー管理システム)」と呼ばれるシステムだ。HEMSに関する標準化を推進している神奈川工科大学の一色正男教授に、スマートハウスの現状や将来の動向を聞いた。

何故、デジタル化するのか?戦略なきIoT活用では競争に勝てない
日本のものづくり企業のIoT活用の可能性について早くから言及し、「つながる工場」の実現に向け、産学連携組織「インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ」の設立にも尽力した、法政大学教授の西岡靖之氏。昨今のIoT、AIブームを分析するともに、日本の製造業が目指すべきIoT活用と新たな課題などについて語った。
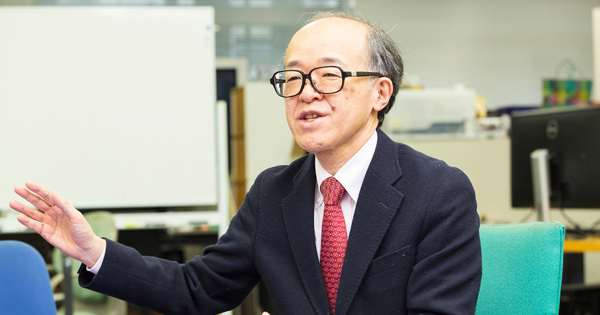
心理学とVRの融合が生む、「行動誘発」の驚くべき威力
前編では、バーチャルリアリティ(VR)の価値は「いかに本物を超えるフェイクを実現するか」だと語った東京大学大学院情報理工学系研究科の廣瀬通孝教授。しかも本物を超えるための重要な観点が「時間軸のコントロール」と言うが、もう一つ教授の中では重要なポイントがある。それが心理学との融合であり「行動誘発」の研究だ。これまでに関わりのなかった分野との連携で続々と生まれる実用化の新領域。後編では最新のVR活用プロジェクトを明らかにする。

トーマツが千葉で始める監査業務のイノベーションと働き方改革
大手監査法人、トーマツが千葉市の海浜幕張副都心エリアに「トーマツ監査イノベーション&デリバリーセンター(AIDC)」を2017年12月1日に開所。同社がここで取り組む「監査イノベーション」について、レポートする。

JR東日本がオープンイノベーション活動のテストマーケティングを開始
JR東日本は、オープンイノベーション型のビジネス創造活動「JR東日本スタートアッププログラム」で採択したビジネス・サービス7つのテストマーケティングを開始。そのうちの3サービスを、2017年11月20日、JR大宮駅にて実施した。その模様をレポートする。

不確実時代を勝ち抜く企業経営の本質を議論
ダイヤモンド社が主催するDIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー・フォーラム『生き残る企業の条件 ―企業変革を迫られている今、経営者は何をすべきか―』が2017年11月20日、東京・経団連会館で開催された。その模様を紹介する。

IoTの本質は現場の最適化ではない 次世代の自社の在り方が問われている
ダイヤモンド社では、2014年10月にガートナー ジャパンの池田武史氏にIoTが産業界にもたらす影響とその対応を聞いた。それから3年が経過したが、インタビューの内容はいまなお陳腐化することなく、経営トップやビジネスパーソンに問いかける。日本企業におけるIoT活用は3年間でどこまで進展したか。そして、進展しなかった要因は何か。2017年11月に再び、聞いた。

日本企業のデジタル変革が突き当たる「壁」をどう越えるか
急速に進展するデジタル社会に対応するため、企業は今、自らも変わる「デジタルトランスフォーメーション(Digital transformation)」に迫られている。そのためには、デジタルを活用した新事業の創造をはじめ、既存ビジネスのデジタル化や、アナログとデジタルの融合による生産性の向上が必要だ。さらにはそれらを実現するための組織・社内ルールの改革、人材育成なども行なっていかなければならない。こうした中、日本企業は今、どのような壁に突き当たっているのか、その壁を乗り越えるために何が必要なのかを考えてみたい。

老舗・歯車メーカーに聞いた「中小企業という弱者の我々が海外市場で勝てた理由」
海外市場に打って出れば、技術力でも、商品力でも、大手企業に負けない絶対の自信がある。けれど、国内市場とは勝手が違う「海外市場での戦い方」がよくわからない――。そんな悩みを抱える中小企業は少なくない。 埼玉県川口市。“鋳物の街”として知られる同市に、売上高40億円の中小企業ながら、産業界で知る人ぞ知る産業用歯車メーカーのKHK(小原歯車工業)がある。技術力に裏打ちされた品質の高さを売りに、今では米国、中国を中心とした20カ国に販路を拡大、海外進出を果たしている同社も、もともとはそうした企業の一つだった。KHK株式会社 中原康輔氏 海外展開を担当する同社の中原康輔氏が言う。「当社は標準歯車で国内シェア7割を持っています。国内ではシェアを守る戦いをしていますが、海外に行くと、我々の知名度はゼロ。逆にシェアを奪いに行かねばならない立場です。当初は、国内と海外では事情が違いすぎて、戦い方が全くわからなかった」 なかでも、日本で成功したビジネスモデルを海外に移植し、販路を拡大していくための物流面での課題は大きかった。が、あるきっかけから“戦い方”を変えてみたところ、一気に視界が開けたという。「それまで誰にも教えてもらえず気付かなかったのですが、物流面を改革することが、中小企業の我々が大手に勝つための、これほど大きな武器になるとは思ってもみなかった」(中原氏)。 結果、同社の昨年度の海外売上高は約6億円に達し、この5年間で1.5倍に成長、今後も毎年1億円ずつの増収を見込むという。KHKの海外展開の「間違いなく競争力の源泉となっている」という物流改革とはいったいどんなものか。詳しく話を聞いた。この記事の詳細は以下からPDFをダウンロードしてお読みいただけます。

ライオンが仕掛けるマーケティング戦略の裏側
毎日何気なくしている洗濯だが、他の家庭ではどんな洗濯の仕方をしているかを知る機会は、意外に少ない。家庭用洗剤を数多く発売しているライオンでは洗剤や洗濯について情報交換ができる「ライオン トップ ファンコミュニティ」を2016年1月にオープンし、1年半で参加者は4万人を超えた。一見地味にみえる洗濯や洗剤でなぜそんなに会話が盛り上がるのか? コミュニティを運営するライオンのキーパーソン3人と運営支援を行うQON(クオン)の担当者2人に話を聞いた。
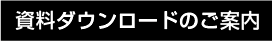
面倒な出張費精算をラクにし、出張情報を一括で可視化できる法人向けサービスとは?
2013年に1000万人だった外国人観光客は2017年には3000万人に迫る勢いだが、同時に宿泊施設のひっ迫も問題となっている。企業では出張する社員から「出張先の宿泊予約が取りにくい」「宿泊費が高騰し予算内に収まりにくい」などの声が上がっており、総務や経理も、出張申請書や出張経費精算の煩雑さに変わりがないのが実情だ。 全国主要都市に57店舗を展開する屋内型トランクルームの最大手企業のキュラーズは、出張の宿泊予約をアウトソースしていたが、社員からは「回答に時間がかかる」「営業時間内にしか対応してもらえない」など不満の声が上がっていた。 そこで楽天トラベルが提供する法人向け出張予約・管理サービス「Racco」(ラッコ)を導入したところ、宿泊予約のみならず、航空券やレンタカーの予約もできるようになったため社員からの評判は上々で、総務、経理担当者もネットで出張情報を一元管理できるようになったため、業務の効率化が図れたという。 アウトソースしていた業務が「Racco」の導入後にどのような効率化が図れたのか? キュラーズ人事総務部のディレクターとマネジャーに導入の経緯と導入後のフロー、そして「働き方改革」にも一役買っているという内幕について詳しく聞いた。この記事の詳細は以下からPDFをダウンロードしてお読みいただけます。経営者、社員、総務・人事・経理が満足する「出張管理システム」 ■出張情報を一元管理できるメリット■スマホで簡単に宿泊予約ができる■総務・経理担当者も出張情報がひと目でわかる■出張コストを可視化でき、経費の削減にもつながる ログインで一部項目の登録が省略できます。情報の修正や追加をおこなった場合は登録内容が更新できます ※必ずお読みくださいこれからご登録いただくあなたの個人情報は楽天株式会社(同社のプライバシー・ポリシーはこちら)に渡されご案内などに利用させていただきます。ダイヤモンド社のプライバシー・ポリシーはこちら。

人材難の中小企業の競争力を向上させる強力な“武器”とは?
もはやITなしではビジネスが成立しない時代。しかし一方で、特に中小企業においてIT活用がなかなか進んでいない現状がある。その背景にあるのが、適切なIT人材の不足である。この課題を解決するカギはどこにあるのか。

ユーザー同士の会話が購買行動へ昇華していく森永乳業のコミュニティサイト「Newの森」
アイスクリームの「pino(ピノ)」や「PARM(パルム)」、「森永アロエヨーグルト」、ギリシャヨーグルトの「パルテノ」、「おいしい低糖質プリン」、その他牛乳や乳製品を製造・販売している森永乳業は2015年7月にコミュニティサイト「Newの森」をオープン。以来2年弱で約3万人の会員規模までに成長した。特筆すべきはサイト内のコメントが他の会員に波及し実際の購買活動につながっている点。サイト運営における情報発信やイベント、キャンペーンの実施状況について、森永乳業のキーマン3人と運営支援を行うクオンに話を聞いた。

ビジネス競争に勝つためのウェルビーイングの実現とコミュニケーション活発化
社員が実際に働く姿を見せる「ライブオフィス」を通じて、常に新しいオフィスを提案してきたコクヨ。その根底には「ウェルビーイング」の考え方がある。それはまた、企業が国際ビジネス競争に勝つための一つの施策でもある。

日本自動車ターミナルが描く大都市物流戦略「メトロポリタン・ロジスティクス」とは?
日本自動車ターミナルが掲げる「メトロポリタン・ロジスティクス」。そのコンセプトは「東京23区内の4つのトラックターミナルで『大都市物流戦略』を実現」すること。これによって、首都圏物流にはどのような変化が起こるのだろうか。「メトロポリタン・ロジスティクス」に不可欠な物流拠点としての4つのアドバンテージ「メトロポリタン・ロジスティクス」とは何か。 日本自動車ターミナルの尾澤克之専務は、そのコンセプトについて「東京という大消費市場において、競争力の高い"大都市物流戦略"を実現するために、物流拠点として求められる要件を示したもの」と定義する。 そして、その要件は4つのアドバンテージ(優位性)で構成されると説明する。 4つのアドバンテージとは「Lead Time Advantage リードタイム・アドバンテージ」、「Labor Advantage レイバー・アドバンテージ」、「Carrier Link Advantage キャリアリンク・アドバンテージ」、「Continuity Advantage コンティニュイティ・アドバンテージ」だという。「リードタイム・アドバンテージ」とは、アクセスに優れ、消費地に近く、高効率な事業展開を可能にするための優位性を指す。「とくにEコマースの分野では、当日配送や1時間配送など、いかに配達時間を短縮できるかが勝負となる。そのためには、消費地に近く、かつアクセスに優れた場所に立地していることが条件になる」(尾澤氏)。 また、スピード・ロジスティクスを実現するためには大型かつ高機能な物流施設であることも必須要件となる。「Eコマースの配送センターは通常、幅広い品揃えを実現して欠品をなくすために、一般小売業の3倍の在庫スペースが必要だといわれている。また、生産性の高い庫内オペレーションを行うためには、マテハン機器を導入できる強い床耐荷重や高い天井高に加え、ワンフロアで作業を完結するために、トラックがフロアに直接乗り入れできるダブルランプウェイなど高機能なスペックが求められる」(同)「レイバー・アドバンテージ」とは、労働力の確保に優れた立地優位性を指す。「最近の物流施設は、物流の小口化、多頻度化が進んだこともあり、ピッキングや流通加工のために多くの庫内従業員が必要となる。ただ、労働力を奪い合う時代を迎えており、ヒトが集まりやすい場所に立地していないと、事業の継続性に支障が出る事態も考えられる。とくにパート・アルバイトの中心となる主婦の方にとっては、通勤時間や駅から近いといったことが勤務の条件となる」(同) また、コンビニやレストラン、休憩室、女性従業員向けのパウダールームなど、施設で働く人々が気持ち良く働けるアメニティ設備が備わっていることも大事な要件のひとつだ。「キャリアリンク・アドバンテージ」とは、陸・海・空の輸送機関(キャリア)との連携や接続、また共同輸配送を実現する上での優位性を意味する。「単独企業だけの効率化は限界に近づいており、これまで以上に生産性の高い物流を実現していくためには、他社との連携や共同化が不可欠な時代を迎えている。また、モーダルシフトを進めるためには鉄道貨物駅などが近くにあること、輸出入貨物など国際物流に対応するためには港や空港に近い場所に立地していることが必要になる。さらに、ドライバー不足が進む中で、"足回り"の確保はより一層大事になってくる。その意味では、近くにトラック運送事業者がいることは大きな安心材料につながる」(同)「コンティニュイティ・アドバンテージ」とは、災害に強く、24時間・365日稼働可能な物流施設であることを示す。「東日本大震災でサプライチェーンが寸断された事例を見ても、ソフト・ハードの両面で災害に強い物流施設であることは絶対条件となる。とくに東京の場合、首都直下型地震が発生するリスクは避けられず、仮に発災した場合でも事業継続性が確保されていることが重要だ」(同) また、都市型の物流施設の場合、地域住民とのトラブルを起こすことなく24時間・365日稼働できる施設であることが、優位性を確保する意味でも大事な条件となるという。「都内にある物流施設の場合、稼働後に周辺の宅地化が進み、騒音などで近隣とトラブルになったり、建替えを行う際に反対運動にあったという話を聞くことが少なくない。その点からも、消費地に近い場所に立地しながらも、周辺に住宅地がないということが物流拠点を選ぶ際の大きなポイントになる」(同)日本自動車ターミナル尾澤克之専務 尾澤氏は、「こうした4つのアドバンテージを兼ね備えた物流施設が、大都市物流戦略を高い次元で実現しようとする場合、競争優位性を発揮するだろう」と総括する。 このような「メトロポリタン・ロジスティクス」の概念を当てはめた場合、日本自動車ターミナルが保有し、管理・運営する4つのトラックターミナルは、いずれも大田区、板橋区、足立区、江戸川区という東京23区内に立地し、各ターミナルとも鉄道駅から徒歩数分という便利な場所にある。 また、40社近いトラック運送事業者がテナントとして入居しており、トラック輸送との連携が容易なほか、トラックターミナルという特性上、主要幹線道路にも近接している。トラック以外の輸送機関との連携についても、港湾や空港、鉄道貨物駅へのアクセスは良好だ。 さらに、72時間連続稼働する非常用自家発電設備が全ターミナルに備わっており、災害対応やBCPの面でも万全を期しているほか、4ターミナルとも物流施設しか建てられない流通業務団地内に立地しているため、周辺に住宅が少なく、24時間・365日稼働も問題なく行うことができる。 そして、同社が「メトロポリタン・ロジスティクス」で提示した新たな概念をより具現化し、新しい時代の"トラックターミナル像"を示す象徴的なアイコンとなるのが、2018年7月に完成する高機能型物流施設「ダイナベース」だ。

首都・東京を物流危機から救う「トラックターミナル」という存在
人手不足など数多くの課題に直面する物流。なかでも、世界有数の消費地である首都「東京」で、効率的な物流を実現することは、想像以上に難しい。50年にわたって都内で公共トラックターミナルを運営し、都市内物流の効率化に貢献してきた日本自動車ターミナル。同社が提示する新たな概念に、新時代の「大都市物流戦略」を構築するためのヒントがある――。(取材・文/「カーゴニュース」編集長 西村旦)日本物流の心臓部「トラックターミナル」 浜松町駅から羽田空港に向かう東京モノレール――。流通センター駅にさしかかる手前で車窓から外を見渡すと、広大な物流施設群が目にとびこんでくる。 日本自動車ターミナルが運営する公共トラックターミナルのひとつ、京浜トラックターミナルだ。東京・平和島にある京浜トラックターミナル 人口1300万人を超える首都「東京」。その巨大都市には昼夜を問わずさまざまな物資が行き交い、都民のくらしや経済を支えている。その膨大な物流の"大動脈"となっているのがトラック輸送であり、そのトラックが円滑な輸送を行うために不可欠な役割を果たす"心臓"ともいえるのがトラックターミナルだ。 日本自動車ターミナルは、この京浜トラックターミナルを含め都内4カ所に公共トラックターミナルを保有し、管理・運営している。総面積は約65万㎡――その規模は実に東京ドーム14個分に相当する。 各ターミナルには日本を代表する各トラック運送事業者が入居し、全国各地から日夜、長距離大型トラックで運ばれてくる貨物を受け入れ、小型トラックに積み替えて都内各地に配送する「結節点」となっている。 もし東京に、物流の"心臓""整流装置"ともいえるトラックターミナルがなかったとしたら――。都内の道路には大型トラックが溢れ、交通混雑はさらに悪化し、東京の都市機能は大幅に低下してしまうことは想像に難くない。 経済や生活の基幹インフラであり、ライフラインでもある物流。その物流を施設面から下支えてきた日本自動車ターミナルはいま、会社設立50周年を機に「第2の創業」ともいえる変革期を迎えている。 ドライバー不足に代表される物流危機が顕在化する一方で、Eコマースの急激な成長などによりサプライチェーンの構造は大きく変化し、さらに高度化されたきめ細かい物流サービスの提供が求められるようになってきている。 そうした環境変化の中で、同社は、東京23区内に広大な物流用地を抱える圧倒的な立地優位性を活かし、物流の進化や高付加価値化に対応した物流拠点として生まれ変わることで、新たなステージに立とうとしている。 トラックターミナルを超えた「トラックターミナル」へ――。その「次なる50年」を見据えた新たな事業戦略の核となるのが、『メトロポリタン・ロジスティクス』という新たな大都市物流の概念だ。

【特別対談】小規模企業の働き方は「電話」から変えられる
小規模な企業にとって固定電話は厄介な問題だ。解決策はあるのか。総務目線で課題解決を図る「戦略総務」の提唱者、豊田健一・『月刊総務』編集長と、スマホで固定電話の番号が使える法人向け通話サービスを開発したニフティの黒田由美さんが、小規模企業の電話の活用法と働き方を考える。

森永乳業の「本当に効く広告」、鍵はコミュニティにあり
牛乳や乳製品、アイスクリーム、飲料などの食品の製造・販売でおなじみの森永乳業。同社マーケティングコミュニケーション部長 寺田文明氏は、「究極の広告とは、個対個の対話である」として、消費者コミュニティをマーケティングに活用する。