デロイト トーマツ グループ
スポンサード先
スポンサード記事
全 49 件中 41 - 49 件を表示

税務環境のパラダイムシフトに対応するために日本企業はマネジメントをどう見直すべきか
OECD(経済協力開発機構)とG20によるBEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトに代表される国際的な課税ルールの変更や、後戻りできないグローバル化の進展、そして税務のデジタル化など、税務環境のパラダイムシフトが加速している。日本企業は今、税務マネジメントの在り方をどう見直すべきなのか。税務部門を戦略的な組織に変革するためにリーダーが今取り組むべきことを、ワークショップを通じて整理できるのが、デロイト トーマツ グループのイノベーション創発施設「Deloitte Greenhouse」で提供する「Tax Transformation Lab」だ。
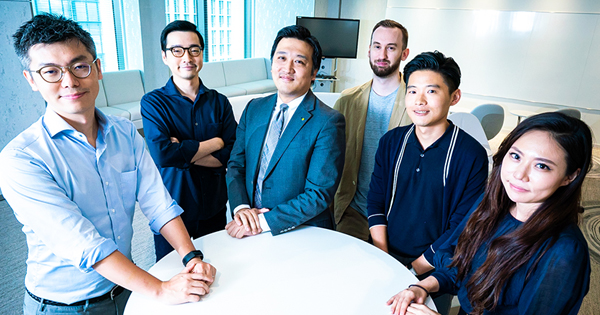
イノベーションへのアプローチを問い直すタイミングがきている
イノベーションが持つ意味は時代とともに変化している。今求められているのは、デザイン思考やデジタル技術活用、スタートアップとのオープンイノベーションなどの取り組みを「魔法の杖」と捉えて単発で実行するのではない。統合的な観点から、社会や顧客の課題起点で新しい価値を創造して市場に浸透させ、かつビジネスとして収益をしっかりと獲得するイノベーション活動だ。デロイト トーマツ グループが今年6月に開設したイノベーション創発施設「Deloitte Greenhouse」(デロイトグリーンハウス、詳細はこちら)では、こうした視点に基づくデロイト トーマツのイノベーション支援を体験できるセッションとして「Innovation Lab」(イノベーションラボ)を展開している。

あるべき経営管理体制に正解はない事業形態に合わせて常に変革する │特別対談│海外成長戦略とグループガバナンス | リーダーシップ|DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー
クロスボーダーM&Aを軸とした攻めの成長戦略を推進するNEC。それに伴い、海外を含むグループガバナンスがますます重要性を増している。法務、コンプライアンス、経営監査、輸出管理の4部門を統括する執行役…

アナリティクスによって組織の未来を切り開くその出発点がデロイト トーマツ「IDO Lab」にある
デロイト トーマツ グループが今年6月に開設したイノベーション創発施設「Deloitte Greenhouse」では、ラボと呼ばれるさまざまなセッションをCxO(経営幹部)向けに提供している。今回はその中から、アナリティクスをテーマとした「IDOラボ」について紹介する。

経営幹部の課題解決に突破口を開く「Deloitte Greenhouse」の全貌
デロイト トーマツ グループは、CxO(経営幹部)の課題解決に特化したイノベーション創発施設「Deloitte Greenhouse」(デロイト グリーンハウス)を東京・丸の内に開設した。日本を含め世界25ヵ国で展開されている同施設は、従来の方法では打開の見込めない経営課題に対し、ブレークスルー(突破口)を見いだすためのハード面、ソフト面の仕掛けが随所に施されている。

革命期に問われるリーダーの自己変革力
2045年に目指すべき社会像を起点とした、日本の社会・経済システムの変革構想「Japan 2.0」を提言してきた経済同友会代表幹事・小林喜光氏と、この「Japan 2.0」の議論にも加わったデロイト トーマツ インスティテュート代表(※)の松江英夫の対談。その後半では、自己変革をけん引すべきリーダー層へのメッセージを中心に活発な議論が続いた。

待つのはユートピアか、ディストピアか岐路に立つ日本、変革の指針を語る
小林喜光氏は経済同友会の代表幹事に就任後、2045年に目指すべき社会像を捉え、そこから逆算して変革を設計する、未来起点の社会構想として「Japan 2.0」を提言してきた。この「Japan 2.0」の議論にも加わり、2019年を日本企業の転換点とするよう提案した、デロイト トーマツ インスティテュート代表(※)の松江英夫が、日本企業を取り巻く現在の環境と変革を推進するリーダーシップの在り方について、小林氏の大局観を聞いた。
不確実な時代には「確実なる底力」がものをいう。今こそ、日本企業は強みの再定義を―― デロイト トーマツ グループが考える「日本企業の3つの指針」とは
ますます先の読めない時代になっている――。これは今、ほとんどの経営者に共通する思いに違いない。しかし、ただ「先が読めない」と言っているばかりでは、企業の舵取りはできない。前進するには、多様な課題を整理し、進むべき航路を定めることが求められる。まさにそうした中、デロイト トーマツ グループから公表されたのが「不確実な時代に強みを再定義~『現場エコシステム』で確実なる底力」だ。同グループの連携を推進する基盤として誕生した「デロイト トーマツ インスティテュート」(DTI)(※)が発行した最新レポートである。そこには、どんなメッセージがあるのか――。DTIの代表を務める松江英夫氏に聞いた。

ガバナンス向上の核心は取締役会の改革にある デロイト トーマツ グループGRCサービス | コーポレートガバナンス|DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー
「監査等委員会設置会社」制度と共に、わが国にもコーポレートガバナンス・コードが導入された。2013年6月に閣議決定され、コード制定の契機ともなった「日本再興戦略」から3年を経ようとする今、企業サイド…