ダイヤモンド・オンライン
ウェブサイトスポンサー企業(記事数上位10社)
掲載記事
全 1,485 件中 1,241 - 1,260 件を表示

進化し続ける“茶カテキン”で「ヘルシア新時代」へ
2003年に発売された『ヘルシア緑茶』は、体脂肪を減らすのを助ける特定保健用食品としてブームを巻き起こした。その研究過程には、茶カテキンの発見と苦味を克服する過程があり、特定保健用食品への険しい道のりや、良質な茶葉を探す努力があった。今スティックタイプの新製品『ヘルシア 茶カテキンの力 緑茶風味』(機能性表示食品)の発売で、ヘルシア新時代の幕が開く。

働き方改革の推進は“Customer First”のために
社員一人ひとりが顧客価値の創出に充てる時間を最大化すべく、システムインテグレーター(SIer)としてみずからも働き方改革の推進に力を入れる日本ビジネスシステムズ。全社員が仕事に使う共通プラットフォームとしてMicrosoft 365(注)を導入し、活用とノウハウの蓄積を進めている。経営者として、この取り組みの先頭で旗を振るのが、同社社長の牧田幸弘氏である。

働き方改革による“創造力向上”が企業の持続的成長の原動力になる
働き方を変えることで社会を変革する手島主税日本マイクロソフト 執行役員 常務クラウド&ソリューション事業本部長 兼 働き方改革推進担当役員クラウド事業を担当し、顧客企業のデジタル・トランスフォーメーションに従事。全社の働き方改革推進および日本の社会変革に向けた取り組み「Workstyle Innovation NEXT」へ注力。編集部(以下青文字):あらためてお聞きします。日本マイクロソフトは、なぜ働き方改革に力を入れるのでしょうか。手島(以下略):今後も少子高齢化に伴う働き手不足が続く中でビジネスを持続的に成長させていくためには、社員一人ひとりの創造力を高め、それを通して組織全体の生産性を向上させていかなければならないからです。 たとえば、マイクロソフトのクラウドをベースとした統合ソリューションであるMicrosoft 365に用意されたTeamsなどのコラボレーション・ツールにより、いつでも、どこにいても、誰とでもつながることで、社員は常に社内外の人々と協働しながら即断即決でスピーディに仕事を進めていくことができます。 また、Microsoft 365の上で仕事をすることにより、それぞれの社員が誰とコラボしながら、どのような業務を行っているのかが透過的となり、活動状況がデータとして蓄積されます。このデータはAIによって分析され、各社員の仕事への取り組み方について「新しいチームメイトのAさんと、もっとコラボしてみてはどうか」「木曜午後の会議の最中にメールを書いていた(集中を欠いていた)が、この会議に出席する必要はあったのか」といったアドバイスや気づきをシステム(MyAnalytics)が与えてくれる。こうした洞察を通じて、社員はみずからの働き方を定期的に見つめ直し、創造性を高めることに時間を割り振ることができます。

効率化から価値最大化へ働き方改革の新ルール
我が国の労働生産性の低さが指摘されるようになって久しい。そうした中、「すべての企業は時代に応じた働き方を取り入れながら、“生み出す価値の最大化”を目指して活動すべき」と語るのは、Microsoft 365を活用した働き方改革の支援でタッグを組む、ネクストリードの小国幸司氏とソフトバンク コマース&サービスの齊藤主典氏だ。

総合力で顧客支援働き方の世界標準化を実現する
富士通グループでは、全世界16万人の社員に協働のプラットフォームとしてOffice 365を導入し、活用ノウハウを蓄積してきた。そのノウハウと、同グループが世界中に構える拠点を活かして、企業の海外進出に伴うOffice 365のグローバルな活用を全面的にサポートできる点が、富士通マーケティングの最大の強みだと同社執行役員の浅香直也氏は話す。

高齢者の食を考えた食事手渡しにこだわり 安否や心配事を確認
宅配した弁当は必ず手渡しして、少しの間、顧客との世間話に花を咲かせる――。シニアライフクリエイトの在宅の高齢者向け弁当の宅配事業「宅配クック123(ワンツウスリー) 」は、「心と体」の両方の健康を保つことを目標としている。高橋 洋シニアライフクリエイト代表取締役 「宅配クック123」は、シニアライフクリエイトの高橋洋社長の「断れない」体験から始まった。1999年のことだ。「私が塾講師をしながら弁当店でアルバイトをしていたとき、店が年内で閉店することになり、二十数人の高齢者に食事の提供ができなくなったのです。でも、『来年からはよその店で食べてください』と断ることは、私にはできませんでした」。 時は暮れも押し迫った12月、高齢者向け宅配弁当のフランチャイズ(FC)本部を立ち上げた。それが「宅配クック123」の始まりである。 「創業当時の高齢者の“食事情”は実につらいものでした。例えば、大衆食堂の出前は1000円以上だったので、無理に品数を多く頼んで半分捨てていたとか、遠くに住む息子に心配を掛けないよう『ちゃんと食べている』と言いながら、菓子パンを食べていたというような話がたくさんありました。そこで、在宅の高齢者の方に安心・安全で安価な食事を届けることを使命としたのです」と高橋社長は振り返る。

家族の代わりに、近くの郵便局社員が会いに行き、様子を伝えてくれる
郵便局のみまもりサービスである「みまもり訪問サービス」は、離れて暮らす親に郵便局社員が会いに行き、生活状況を聞き取り報告するサービス。相手が“郵便局の人”だから、高齢の親御さんも安心して迎えることができる。訪問先ではどんな会話が交わされるのか。相模原郵便局の訪問に同行した。
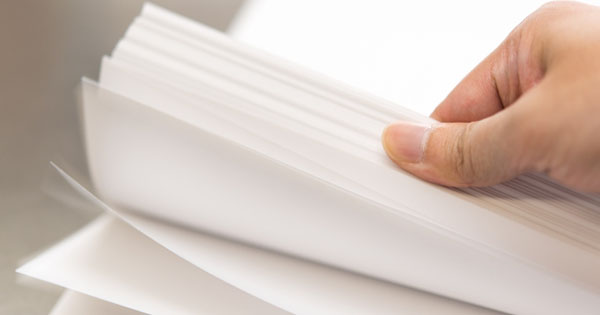
独創技術で紙の未来を変え企業や自治体のSDGs達成に貢献する
エプソンが開発した「PaperLab(ペーパーラボ)」は、使用済みの紙から新たな紙を生み出す画期的なプロダクトだ。持続可能な社会の実現を目指す技術であり、企業や自治体などのSDGs達成に貢献する。その意義と可能性を、SDGsに詳しい笹谷秀光氏に聞いた。笹谷秀光CSR/SDGsコンサルタント、伊藤園顧問、日本経営倫理学会理事、グローバルビジネス学会理事。東京大学法学部を卒業後、農林省(現農林水産省)に入省、2008年に退官し、伊藤園に入社。同社取締役を経て、18年より現職 セイコーエプソングループの経営理念は、社会にとって「なくてはならない会社」になること。これはSDGs(持続可能な開発目標)の目的である「持続可能な社会の実現」と一致する。 もともと同社は、創業以来、環境への貢献をはじめ、さまざまな社会課題の解決につながる製品やサービスを創出してきた。つまり、独自の技術力で新しい価値を創造し続けてきた同社にとって、取り組むべきSDGsとは、同社の理念と実績の延長線上にあるとも言えるのだ。 エプソンの「PaperLab(ペーパーラボ)」は、まさに独自の技術力による新たな価値の創造であり、SDGsの目標達成に貢献する製品として注目を集めている。

スマートハウスを普及させるには業界の壁を越えた 幅広い知識を持った人材が不可欠だ。
エネルギー問題や少子・高齢化などの諸問題を、”住まい”と”暮らし”の観点から解決する切り口として注目されているスマートハウス。一般財団法人 家電製品協会は、 その普及に向けた人材育成のため、「スマートマスター」という資格制度を新設した。スマートハウスの将来や、普及を担う人材に求められる能力などについて、東洋大学情報連携学部学部長の坂村健氏に聞いた。古くて新しいスマートハウスの概念坂村 健 (さかむら・けん)INIAD(東洋大学情報連携学部)学部長、東京大学名誉教授、YRPユビキタス・ネットワーキング研究所長。工学博士。1951年東京都生まれ。1984年からオープンなコンピューターアーキテクチャ「TRON」を構築。携帯電話などの組込OSとして世界中で多数使われている。IoT社会実現のための研究を推進。2003年紫綬褒章、2006年日本学士院賞受賞。『ユビキタスとは何か』『コンピューターがネットと出会ったら』『オープンIoT考え方と実践』など著書多数。 “課題先進国”といわれる日本。中でも急速に進む少子・高齢化は、医療・介護予算の膨張や独居老人の増加など、他の国が経験してない段階に入ろうとしている。 一方、産業や生活を支えるエネルギーの大半を石油や天然ガスなどの化石燃料に依存し、その大部分を輸入に頼っているわが国にとって、エネルギー問題は終わりなき課題だ。 これらの問題を“住まい”と“暮らし”という観点から解決する切り口となるのが「スマートハウス」である。 スマートハウスの定義はさまざまだが、家電製品協会では、①省エネルギーな“住まい”(高気密・高断熱、HEMS[ホーム・エネルギー・マネジメント・システム]による制御、太陽光発電・エネファーム・蓄電池などを備えた家)、②安全・安心・快適な“暮らし”(家電機器、住設機器などと、IoT、AI、クラウド、ビッグデータ、ロボットなどによる付加価値を備えた暮らし)と定めている。 ②は、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスを使って、外出先からエアコンのスイッチを入れたり、AIがあらかじめ学習させておいたプログラムに沿って、室内の温度や湿度を自動的に制御したりするイメージだ。AIやIoTの進化によって、こうしたサービスはかなり実現された。「システムやネットワークによって家電を制御するという考え方は、特に目新しいものではありません。日本では、すでに数十年前から大手家電メーカーなどが、現在のスマートハウスと同様の“ネットワーク化された家”を提案してきたのです」と、坂村健教授は説明する。

営業力でOtoO市場をリード19期連続で増収増益、成長し続ける企業の条件とは
創業者である廣瀨勝司社長の個人事業からスタートしたエス・ケイ通信。中小規模の店舗経営に必要な集客や顧客管理のため、効果的なワンストップソリューションを提供、強力で緻密な営業力を武器に、市場規模の拡大するOtoO市場で進化と成長を続けている。エス・ケイ通信廣瀨勝司 代表取締役 中小零細法人を中心に、集客プロモーションのITサービスをワンストップで提供するエス・ケイ通信。拡大するオンライン・トゥ・オフライン(OtoO)市場で圧倒的な強みを持ち、2000年の創業以来19期連続で増収増益を続けている。 代表的なプロダクトは、SEO(※)効果のあるホームページや、SEO対策とは異なる角度で幅広い層(潜在顧客)へアプローチできるランディングページの提供だ。 例えば、同社が提供するホームページでは、訴求したい情報を的確にターゲットに発信できるよう、対策すべきキーワードが自動提案される独自のシステムを搭載。顧客がロングテール(検索ニーズの少ない言葉で、より多くの誘導数を確保するキーワード)をブログに書き込むことで、SEO効果を高めることができる仕組みを構築している。 「広告費をかければ検索エンジンで、上位に表示させることは可能ですが、当社のお客さまである中小企業や小規模店舗の方々は、そこまでの予算をお持ちでないケースが多い。当社のサービスは事業意欲のあるお客さまが使いこなせば、低コストで大きな効果が上げられるものです。導入後もサポートセンターを通じてサイトの進化を促進し、お客さまに寄り添いながら、目的意識の高いユーザーの効果的な集客を実現しています」 そう語るのは、創業者である廣瀨勝司社長だ。※SEO……検索エンジン最適化(Search Engine Optimization)

スマート化する“住まい”と“暮らし”のスペシャリスト「スマートマスター」
政府が目指す「スマート社会」の中で、急速な普及が期待されているのが今話題の「スマートハウス」。そのコーディネートやアドバイスの知識・スキルを持つ専門家に与えられる日本初の認定資格が「スマートマスター」だ。今後、スマートハウスビジネスにおいて需要が高まることは確実。特に住宅の設計・販売、リフォーム、電気工事、家電製品販売などに携わっているなら、今のうちに取得しておこう。社会的課題が最新技術で解決できる時代に森 拓生家電製品協会 認定センター センター長 最近よく耳にする「スマート社会」とは、簡単にいうとAI(人工知能)やビッグデータ、IoT、ロボットなどの最新技術を組み合わせて経済発展や社会的課題の解決を図り、人々に豊かさをもたらす社会のこと。その喫緊の課題として挙がっているのが、エネルギー問題と少子高齢化対策に端を発する諸問題への対応だ。一般財団法人家電製品協会認定センターの森センター長は次のように話す。「エネルギー対策については、日本はパリ協定に基づき、2030年度の温室効果ガスの排出を対13年度比で26%削減するという目標を掲げています。最も厳しく目標設定されたのが家庭部門で39%の削減が必要。こうした温暖化対策にも、進化を続けるテクノロジーが活用できる環境になっています」 その施策として今、政府が推進しているのが「ZEH(ゼッチ:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」だ。これは、住宅の断熱性能の向上や省エネ家電などによって大幅な省エネを実現すると同時に、再生可能エネルギーの導入で電力を社会に供給し、年間のエネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指す住宅のこと。政府は、ZEHを20年までに新築注文住宅の過半数を、30年までには新築住宅について平均でZEHにする目標を掲げている。 一方、少子高齢化に端を発して増加する在宅介護や独り暮らしのお年寄り問題に対し、IoT・AI、ロボットなどと家電が連携したサポートサービスが始まっている。

セキュリティ先進国イスラエルの製品を日本の事情に合うサポートで届ける
世界有数のサイバーセキュリティ先進国、イスラエルのセキュリティ製品の取り扱いと技術サポートをしているのが、インテリジェント ウェイブだ。もはや完全には防御しきれないサイバー攻撃にどのように立ち向かえばいいのか。攻撃者を囮情報であぶりだし、攻撃を防止する製品など、同社が提供する先進的ツールにその答えがある。"攻撃を受けること"を前提とした対策が必須手塚 弘章インテリジェント ウェイブセキュリティソリューション本部長 サイバー攻撃はもはや防御し切れない状況になっている。攻撃ツールの改変や組み合わせによって、防御・検知されないように日々高度化しているからだ。しかも、攻撃者は個人からエコシステムが確立された組織的活動へと移り変わっている。このため、現在のサイバーセキュリティについて、手塚弘章本部長は次の点を指摘する。「防御を回避する新たな手口を次々と繰り出してくる攻撃を、完全に防御するのは無理ですから、“攻撃を受けること”を前提とした対策が必須です」 では、具体的にどうすればいいのか。「攻撃自体が成立しない環境を作り出す『攻撃の無効化』や、進行中の隠れた脅威を検出したり侵入者の行動をリアルタイムに検知する『事前対策の拡充』、攻撃事実を確実に検出し、分析と対応を迅速化する『確実な事後対策と迅速な対応』という三つの対策が求められます」(手塚本部長) そうした対策ができるセキュリティ製品を数多く開発しているのが、国家戦略としてサイバーセキュリティに力を注ぐイスラエルの企業だ。強力な軍事力を持ち、世界屈指のサイバー軍も保有するイスラエルでは、軍で培った技術の民間への転用も進んでいる。その特徴はズバリ、攻撃者の目線で作られたセキュリティだ。 手塚本部長は同国を年に数回訪問し、最先端のセキュリティ製品をチェック。その中から、特に優れた先進的なサイバーセキュリティ製品と技術サポートを日本企業に提供している。

Special Report経産省が推進する「デジタル・トランスフォーメーション(DX)」。それを先駆的に取り入れて省力化・省コスト化と品質向上を両立した先進企業を訪ねた
ビジネスの「デジタル化」とは、人工知能(AI)やIoT(モノのインターネット)などに関する先端的な技術を活用して、既存のビジネスを変革したり、新たなビジネスを生み出すこと。経済産業省が推進する「デジタル・トランスフォーメーション(DX)」は、デジタル化の推進により従来のビジネスや組織を変革し、新たな付加価値を生み出すことを目指す。そこで早い時期からDXを推進し、現場のスマート化を達成し、さらにその先を目指している先進企業のソニーセミコンダクタマニュファクチャリングと中部電力のケースを取り上げ、現場がどのように変革したのかを、経産省の取り組みを含めてお伝えする。

前年比143.8%のブランドも。フランス車がイマ売れる、5つの理由
輸入車と聞くと、あなたはどこの国を最初に思い浮かべるだろうか? 同様の質問をダイヤモンド・オンライン読者にアンケート調査したところ、実に93.5%がドイツと回答。イタリア(3.23%)、アメリカ(1.99%)、スウェーデン(0.74%)と続き、5番目にフランスとイギリスが0.50%で並ぶ。しかし新車販売台数を見ると、影が薄いはずのフランス車の存在感が増しつつあり、なかには前年度比143.8%のブランドも。なぜ今、フランス車が売れるのか? その理由を探る。 日本自動車販売協会連合会によると、国内の新車販売台数は、2年ほど前年比割が続き(2015年度90.7%、2016年度98.5%)、2017年度になりようやくプラスに転じた。拡大画像表示 それでも、その数字は105.3%。輸入車を見ても、販売台数トップ3ブランドはメルセデス・ベンツ:101.4%、BMW:100.9%、フォルクスワーゲン:100.9%と、いずれもほぼ前年度と同台数にとどまっている。 こうした数字と比較すると、フランス車の異質さが目立つ。プジョー:118.6%、ルノー:113.7%、シトロエンにいたっては143.8%と、2桁を軽々越える数字を記録した。自動車が売れないと言われるこの時代に、なぜフランス車はこれほどまでに好調なのか? 冒頭の読者調査結果からも分かるように、多くの日本人にとってフランス車は身近とは言えない。「フランス車に乗ったことがあるか?」という質問にイエスと答えたのは14.39%。ほとんどの人は、購入はおろか、乗ったこともないというのが実情だ。そんななかで、人々はフランス車にどのようなイメージを持っているのか? 次のグラフは、国産車、輸入車全体、フランス車それぞれへのイメージを聞いた結果を比較したものだ。拡大画像表示 やはりフランス車へのイメージはおぼろげなのか、回答結果は国産車と輸入車の中間といったところ。価格が手頃で、基本性能の信頼感が高い国産車。デザインに優れ、先進的な取組も行う輸入車。フランス車は、概ね輸入車寄りながら、その中では手が届きやすいといったイメージだろうか。あえて特徴を探すとすれば、「オリジナリティがある」という回答が国産車、輸入車よりも多く、反対に「技術力が高い」という回答が最も少ないこと。 フリーワードのコメントを拾っても、「独創的で似ている車がない。それでも”あり”と思わされる。(50代男性)」「他にないユニークなデザイン(50代男性)」といった、デザインや設計思想の独創性を評価するコメントが目立った。技術面に関しては、「ネコ足と呼ばれるサスがイメージにあり、体験してみたい(60代男性)」など、乗り心地に関する高評価がある一方で、「故障が多い(50代男性)」「デザイン重視で、車本来の性能については「?」という印象(50代男性)」と、基本性能への疑問の声があがっている。

社員の成長こそが企業競争力になる働きやすい環境整備は欠かせない投資
アドバンテッジ リスク マネジメント社長の鳥越慎二氏がホストを務め、人材戦略と健康経営への取り組みについて語り合うシリーズ対談をお届けする。第1回のゲストには三菱商事の広報・人事部門を担当する常務執行役員の村越晃氏を迎え、三菱商事らしい新しい働き方と新たな中期経営計画に基づく人材育成のビジョンを聞いた。エンゲージメントの高さに特徴鳥越:当社のデータによれば、御社の従業員の仕事に対するエンゲージメントは、他社と比較しても非常に高くなっています。その要因についてどうお考えですか。三菱商事取締役常務執行役員 村越晃氏村越:商社は生産設備などの有形資産をあまり持ちませんから、間違いなく人が最大の資産です。働きやすい環境のなかで社員一人ひとりが成長し、能力を最大限に発揮することでしか、組織としての競争力を発揮できませんし、それがなければ会社としての発展もありません。ですから、働きやすい環境づくりに投資を惜しまないのは、メーカーが研究開発投資、設備投資を惜しまないのと同じことです。 それを前提としたうえで、なぜワークエンゲージメントが高いのかを考えてみると、やはり人が働きがいを感じるのは、いかに自分が必要とされているか、自分が活躍できるフィールドがあるかを実感できたときだと思います。 かつて「商社冬の時代」といわれ、トレーディング主体の商社は中抜きされ、社会から必要とされなくなると指摘された時代がありました。その後、我々はトレーディングから資源や事業に投資して利益を得る「事業投資」へ、さらに現在は、関わる事業に人材を送り、大きく育てる「事業経営」へとビジネスモデルを変革し、会社を発展させることができました。 ただ、この変革はカリスマ経営者がトップダウンで実行したものではなく、一つひとつの事業ユニット、一人ひとりの社員が、対面する業種・業界の求められている変化に向き合い、自分たちは次にどうすべきかを懸命に考え、自らを変化させてきた、その積み重ねの結果です。 自ら変化できるというのは、自ら成長していけるということでもあります。自らを変化させた結果、取引先やパートナー企業から必要とされ続け、活躍できるフィールドが新たに広がっていった。そこに成長実感や働きがいを感じている社員が多いのかもしれません。鳥越:そもそも「変化に向き合い、自らを変化させ、成長させる」というその人自身の基本的な姿勢が必要です。弊社ではそれを「メンタルタフネス」と呼び、意識的に身につけることを推奨しています。御社の場合は、社員の方々がそうした資質を持っており、さらには環境変化によってその資質が強化されていったのかもしれません。御社にはもともと成長意欲の高い人が集まっているのでしょうか。村越:採用にあたって「自ら成長していくんだ」という強い意欲があるかどうかを重視しているのは確かです。アドバンテッジ リスク マネジメント代表取締役社長 鳥越慎二氏 鳥越:採用段階で成長欲求を見極めるのは、難しいのではないですか。村越:おっしゃる通り、人の本質を見抜くのは簡単ではありません。 採用担当者や面接官には、「入社後に修正できる資質やスキルでは選ばないでくれ」と言っています。書類選考やペーパーテストで絞り込むのは応募された方の半数程度までで、そこから先は30代の若手、40代の中堅、50歳前後の部長クラスによる3段階の面接で選びます。役員面接はなく、部長クラスが最終面接です。 新入社員と役員が一緒に仕事をする機会はめったにありませんし、あったとしてもほんの短い時間です。でも、30代は「自分と一緒に働く人たち」、40代は「10年後の頼れる中堅社員」、部長クラスは「将来を託せる人材」という、より長期的かつ身近な目線で人を見ることができる。つまりは、「未来の仲間として一緒に働きたいと思えるか」が、面接における最大の判断基準です。結果として、我々が求めている人材を採用できていると思います。(この資料のダウンロード期間は終了いたしました)

相続を「争族」にしないきめ細やかなサポート力 【税理士法人AKJパートナーズ】
税理士法人AKJパートナーズは、税理士19名、公認会計士11名のほかに、米国公認会計士、社会保険労務士、CFP/AFP等多分野のプロフェッショナルを擁するコンサルティングファームである。
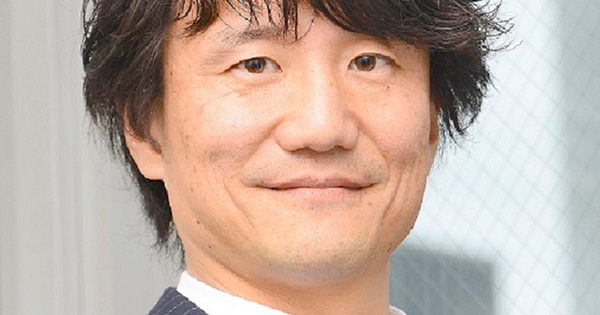
医療法人の相続対策に実績 円満相続を何より重視 【税理士法人鶴田会計】
税理士法人鶴田会計は、愛知・岐阜・三重を主な営業エリアとして、企業経営者や開業医、医療法人などの税務並びに相続相談のサービスを行っている。
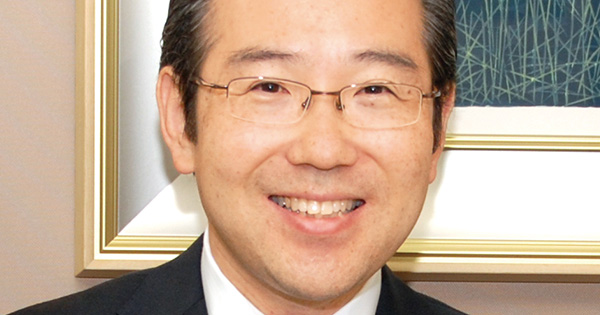
都心の一等地へ資産を組み替える相続事前コンサルティングに注力 【芦原会計事務所】
芦原会計事務所は、相続の事前対策コンサルティングを得意とする税理士事務所である。主な顧客は、不動産貸付業(地主/ビル・マンション経営)と大会社創業者一族で、この2つで関与比率は50%を超える。

適正申告をミッションとする地域に根ざした専門税理士 【風岡範哉税理士事務所】
「税金は高すぎて過払いになることを避け、また低すぎて税務署から指摘されることを避ける」をミッションにする風岡範哉税理士事務所は、静岡を拠点に地域に根ざした相続の専門家として活動している。

節税対策にとどまらない「心」を大切にする円満相続 【タックスパートナー税理士法人】
タックスパートナー税理士法人の大塚理之代表社員は、「単なる節税だけを重視する相続対策ではなく、何よりもお客様の幸せを第一に円満相続の実現を目指すお手伝いを心掛けています」と語る。