掲載記事
全 1,555 件中 441 - 460 件を表示

直接会って聞いた生の声を作品に落とし込む 特別連載(第5回)映画監督・河瀨直美氏
1990年代から作品づくりを始め、97年に劇場映画デビュー作『萌の朱雀』にて第50回カンヌ国際映画祭カメラ・ドール(新人監督賞)を史上最年少で受賞。その後も精力的な活動を続ける世界的な映画監督、河瀨直美氏。独自の世界観を持つ作品はどのように生み出されるのか──。現場や俳優との向き合い方などについて聞いた。

"持続可能な"素材であるアルミニウムの可能性を追求する サステナビリティ経営のこれからを考える
日本発のグローバルなアルミニウム総合メーカーとして、年間130万トンを超える世界トップクラスの生産量を誇り、幅広い分野に製品を提供するUACJ。サステナビリティ経営を重視する同社の石原美幸社長が、SDGs研究の第一人者である慶應義塾大学大学院の蟹江憲史教授とリモート対談。アルミニウムの可能性や今後求められる事業姿勢などについて語り合った。

世界遺産を修復する「道普請」を通じ"持続可能性"の本質を体感できる 多くの企業が「また参加したい」と評価する熊野古道での取り組み
特別レポート企業と地域が取り組む社会課題解決の最前線環境や社会の持続可能性に配慮することで、自社の持続可能性も高めていく──。サステナビリティ経営の視点は、今や企業にとって欠かせないものとなっている…

建学の精神「至誠一貫」の下、地域医療の充実にも貢献を 次代を担う「医療人」を追求する昭和大学③
進行する超高齢社会に耐え得る医療提供体制の構築に向けて、地域医療の重要性が増している。一方で、担い手である医師の確保をはじめ、課題も少なくない。行政、医療現場、教育機関は今、どのような取り組みを進めているのか──。静岡県の川勝平太知事、静岡県医師会の紀平幸一会長、さらに医学部入学試験定員に静岡県地域枠を設定している昭和大学の久光正学長が語り合った。

クルマ好き夫婦は、事故のない世界を目指す自動車保険「&e」をどう見た? スポーツライター・金子達仁さん&フリーアナウンサー・八塩圭子さんの本音対談
スポーツライターの金子達仁さんは、2006年から5年間、日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員も務めたほどのクルマ好き。妻でフリーアナウンサーの八塩圭子さんも運転好きを自認する。そんな二人に、金子家のカーライフや、お互いの運転について尋ねた。また、イーデザイン損害保険(以下、イーデザイン損保)から発売された、「事故のない世界を目指す」をコンセプトにした、まったく新しい自動車保険「&e(アンディー)」の感想を聞いた。さて、二人の評価は?

今がピークか、これからか──投資対象としてのAIの可能性 好調の「グローバルAIファンド」、その背景にあるもの
今、AI研究の最前線はどうなっているのか。投資対象としてのAI関連企業の可能性をどう見るべきか。オムロン サイニックエックスでAI研究者として活動する牛久祥孝氏と、投資信託「グローバルAIファンド」を設定・運用する三井住友DSアセットマネジメントの渡辺英茂氏、同ファンドの実質的な運用を担当するアリアンツ・グローバル・インベスターズの滝沢圭氏に聞いた。
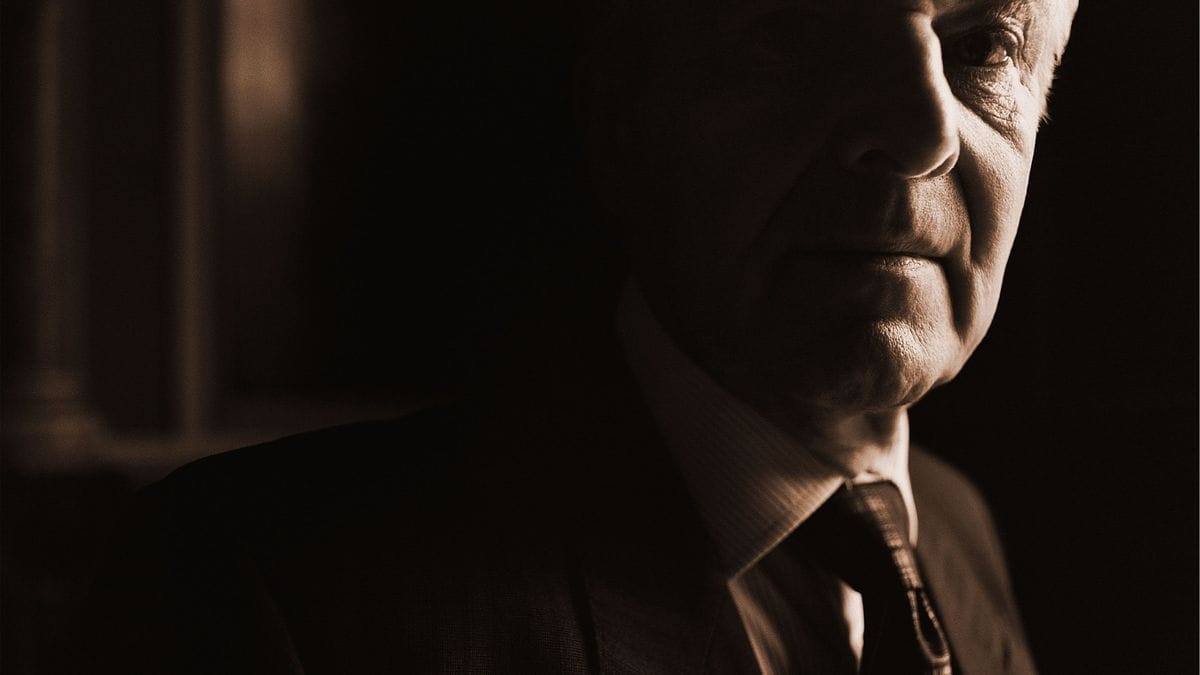
統合シナジーに手応え。幅広い領域でポテンシャルを発揮していく 柳井隆博 三菱HCキャピタル株式会社 代表取締役 社長執行役員
2021年4月、三菱UFJリースと日立キャピタルが経営統合して誕生した「三菱HCキャピタル」。昨年末には、持続的に成長する上で優先的に取り組むべきテーマとして、6つの「マテリアリティ(重要課題)」を特定。さらに、経営理念の実現に向けた「経営の中長期的方向性」の在り方、その具現化の第一弾となる2023年4月にスタート予定の「中期経営計画」策定に関する議論も活発化するなど、目指す未来像が徐々に鮮明化しつつある。「PMI(Post Merger Integration)は極めて順調。旧両社の強みが足し算から掛け算へと移行していく手応えを実感しています」と語るのは、代表取締役 社長執行役員の柳井隆博氏だ。同社のポテンシャルを発揮できるフィールドは広い。社会にどのような価値を示すのか、その思いを聞いた。

入山章栄教授が全リーダーに説く「これからの時代に必要な意識改革」 経営からヘルスケアまで通ずる「量から質へ」の転換
ビジネスを取り巻く環境が大きく変わり、企業経営にも変化が求められている。先行きが不確かな時にこそ立ち返るべきはセオリー、経営理論である。国内外の企業の経営を研究する入山章栄教授がキーワードとして挙げるのが「企業文化」と「習慣化」だ。企業経営のみならず、個人のクオリティー・オブ・ライフの向上にもつながるような第一人者の金言をお届けする。

開発途上国の人々が「命を輝かせる」日本の国際協力 対等な立場で手を取り合う活動は、日本人にとっての誇りであり、心の豊かさにつながる
気候変動による地球規模の自然災害、新型コロナウイルス感染症の蔓延、紛争問題の深刻化――。地球環境や国際情勢が激変するなか、国際協力、国際協調の重要性はますます高まっている。そこで今回、日本の国際協力の実施機関である独立行政法人国際協力機構(JICA)の北岡伸一理事長と、世界で活躍する映画監督の河瀨直美氏の2人による特別対談を行った。活躍するフィールドは異なるものの、北岡理事長と河瀨監督はともにグローバルな舞台で活躍し、「日本(人)ならでは」といえる活動や表現により世界各国から高い評価を得ている。両者が対談で、日本が世界に向けて発信すべきこと、日本にふさわしい国際協力の未来像などを熱く語り合った内容をここで紹介する。

慶應義塾中等部が導入する、実社会で役立つ英語テスト 英語4技能を伸ばす!
名門・慶應義塾中等部の生徒が受験する「TOEIC Bridge® Tests」。学校や塾のテストではなかなか測ることが難しい、真の「英語コミュニケーション能力」を測定できるという。

先が読めない世界で日本が生き残るためにやるべきこととは? 強みが活かせるフィールドでの勝負、人づくり、官民のスクラムが鍵になる
新型コロナウイルスの感染拡大や地球温暖化といった世界規模の課題が次々と押し寄せ、DX(デジタルトランスフォーメーション)やAI(人口知能)といった新しいテクノロジーの話を見聞きしない日はない。国際情勢に目を向ければ、米中両国の対立が激化するなど混迷の様相を深めている。このように変化のスピードが加速し、先が読めない時代が到来している中、日本が生き残るためにどうしたらいいか――。

「事故にあわない」新しい自動車保険「&e(アンディー)」を記者が試乗体感 事故のない世界そのものを、ユーザーと共に創る
2021年11月、イーデザイン損害保険(以下、イーデザイン損保)から、まったく新しいタイプの自動車保険が発売された。「デジタル時代の共創型自動車保険」を謳う「&e(アンディー)」は、従来の「事故を起こしてから使う保険」ではなく、「事故にあわない保険」をコンセプトにしている。確かに事故にあわないということは、すべてのドライバーの願いだが、保険でどうやってそれを実現するのか? 記者が実際に試乗し、体感してみた。

「Slackの絵文字コミュニケーションで組織を変革」ディップが手に入れた絶大な効果とは? 業務の効率化と情報共有、連携を同時に実現
コロナ禍のリモートワークで浮き彫りになった課題を解決するため、求人情報サービス「バイトル」「はたらこねっと」などを展開しているディップが全社統一のコミュニケーション基盤として採用したのが、ビジネス向けのメッセージプラットフォーム「Slack(スラック)」だ。その効果は導入後すぐに現れたという――。同社でSlack導入プロジェクトを推進した西野翠氏と、Slack導入アンバサダーを務めた髙野麻衣氏に、Slackを使った業務効率化や、絵文字機能を使って組織の連帯感を高める方法など、同社の導入事例を詳しく聞いた。
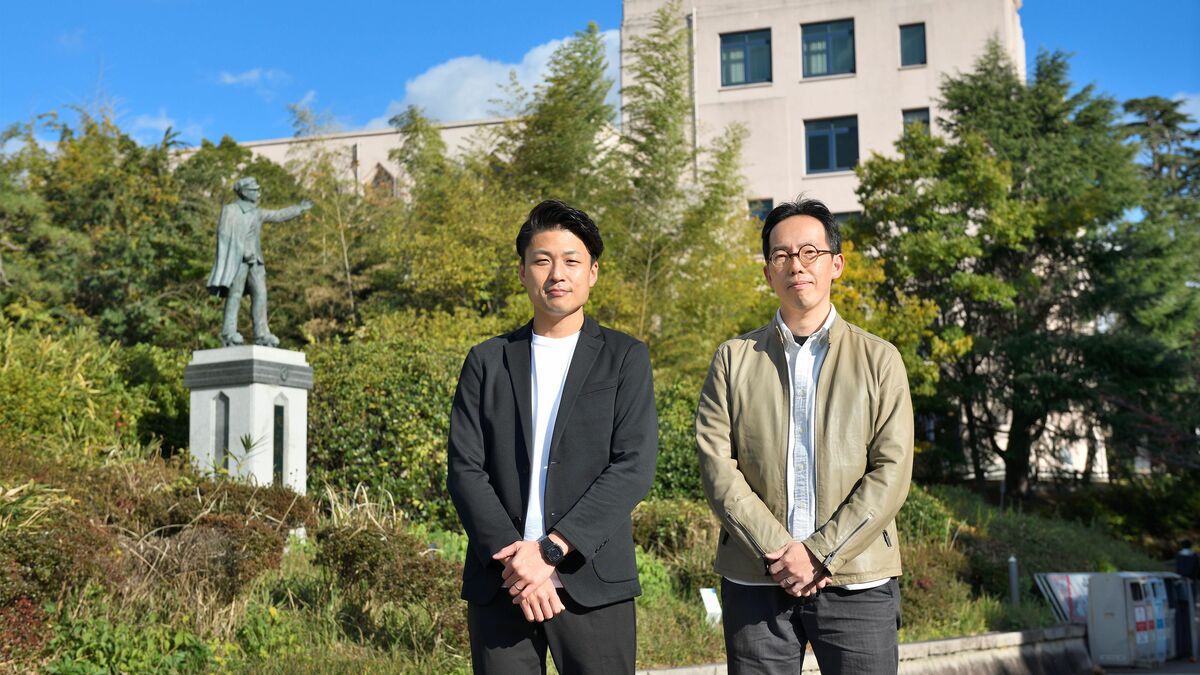
ついついマナーが向上する喫煙所プロジェクトが始動! 行動変容を促す日本発のフレームワーク「仕掛学」を駆使
分煙が徹底され、喫煙に関するマナーも向上すれば、たばこを吸う人と吸わない人との軋轢もなくなるはず。多様性が尊重される時代であるだけに、両者の共存は社会的に重要なテーマ。この問題に正面から挑むのが「仕掛学×喫煙所」プロジェクトで、人間の好奇心を刺激することで喫煙マナーが自然と向上するという。仕掛学の提唱者である大阪大学大学院の松村真宏教授と、同プロジェクトリーダーである田中洋平氏(JT)の2人に対談してもらった。
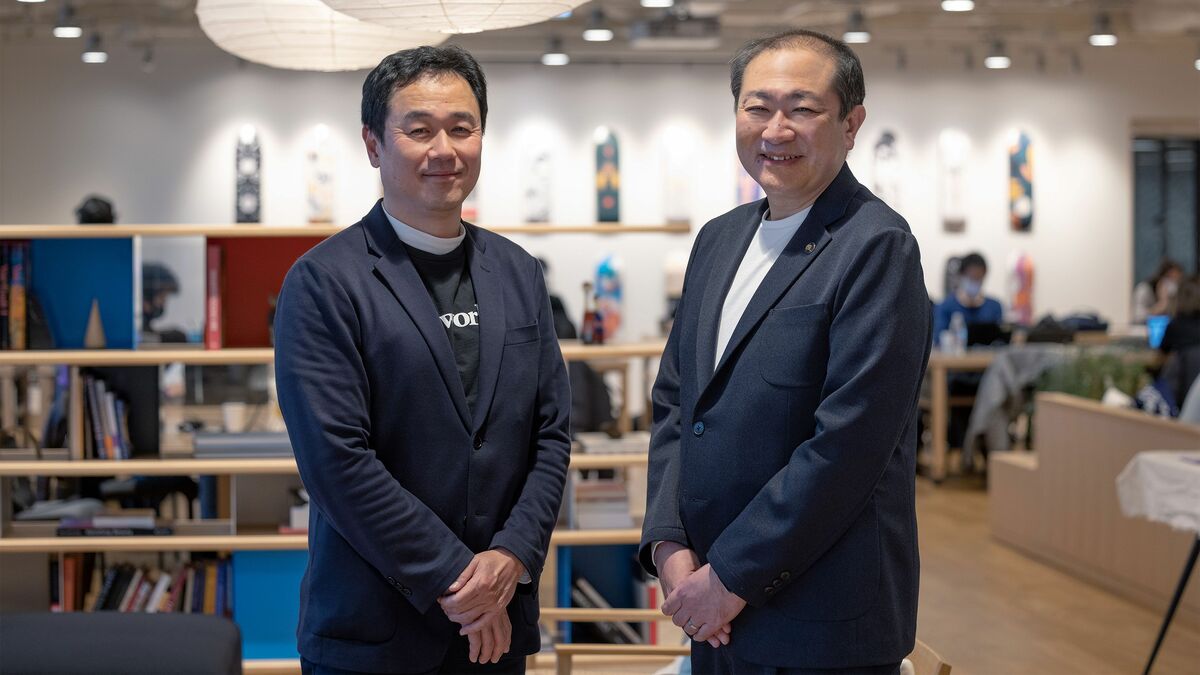
相互に利益がある真の「公民連携」を地域活性化の推進力に 【対談】守屋輝彦(小田原市長)×ジョニー・ユー(WeWork Japan CEO)
豊かな自然環境と都市機能を併せ持ち、歴史や文化、食などの面でも充実した資産を有する神奈川県小田原市。現在、「世界が憧れるまち“小田原”」を掲げ、独自のまちづくりを推進中だ。あらゆる取り組みの中で「公民連携」を重視する同市は、昨年6月、民間企業などとの交流を深めるべく、WeWork渋谷スクランブルスクエアへの入居も果たしている。そこで今回、守屋輝彦小田原市長とWeWork Japan(※1)のジョニー・ユーCEOが対談。公民連携の意義や可能性などについて語り合った。

地域の力を成長につなげるために知っておきたいこと 確かな情報が立地戦略を支える
経営環境が大きく変化し、先行きの不透明感も強まる中、事業拠点の立地についてもいっそうの戦略性が求められている。戦略立案に当たり、経営層などが知っておきたいポイントをレポートする。

言葉や文章だけで信頼関係を築くのはとても難しい 特別連載(第4回)脳科学者 医学博士 認知科学者・中野信子氏
コロナ禍は、私たちのコミュニケーションの在り方にも大きな影響を与えている。リモートワークが浸透する中、「直接人と会うことの価値を再認識した」という声は多い。人が、空間や時間を共有する意義はいったいどこにあるのか──。脳科学、認知科学を専門とする中野信子氏に聞いた。

未来に挑戦する企業に山梨県が選ばれる理由とは 2つの事例から読み解く「テストベッド」としての価値
山梨は、挑戦と近い。未来と近い──。近い将来、リニア中央新幹線が開業することにより、アクセス面の飛躍的な向上が見込まれる山梨県。2020年3月には「リニアやまなしビジョン」を策定するなど、開業後を見据えた取り組みが着々と進行中だ。その一環として力を入れているのが、多くのスタートアップなどの最先端企業を山梨に呼び込むための「TRY! YAMANASHI! 実証実験サポート事業」。同事業に採択された企業の生の声なども参考にしながら、「テストベッド」としての山梨の価値について考えてみる。

さらに手厚くなった支援策で成長と復興が加速する 「本社機能の移転」を後押しする独自の補助金を新設
持続的な経済成長と復興への歩みをより力強いものに──。企業誘致において積極的な施策を打ち出す福島県は、2021年に「転居費用を1人当たり最大で100万円補助」する「福島県本社機能移転促進事業費補助金」を新設した。国の税制優遇措置「地方拠点強化税制」と併せて活用できるのが特徴だ。手厚さが増した支援策の展開で、本社機能の移転や拡充を目指す企業のチャレンジを後押しする。

「体験型ワーケーション」は心と体にどんな変化を起こしたか? 明らかになりつつある「農泊」のエビデンス
社員のパフォーマンスを向上させるには、どのようなワーケーションが効果的なのか──。地域滞在での各種体験と、ストレス軽減や幸福度との関係性が明らかになりつつある。順天堂大学緩和医療学研究室の千葉吉史氏は「効果が得られやすい人の傾向なども把握可能です。リフレッシュ、モチベーションアップ、コミュニケーション活性化など、エビデンスに基づく明確な目的を定めたワーケーション導入が広がるでしょう」と語る。