スポンサード記事
全 13 件中 1 - 13 件を表示

高校の「情報」科目への対応、待ったなし 「情報」教育を深化するために必要なこととは? - 教育とICT Online
高校教育では「情報」教育の深化が急務になっている。2025年には大学入学共通テストで「情報I」が出題科目として追加される。スプリックスの島貫氏とNPO法人さかてらプレイスの鈴木氏が、学校現場の現状や課題、情報教育の未来について語った。

大阪教育大学・スプリックス 特別座談会 教科「情報」の学びの深化に向けて――教育現場の情報教育と教員養成のこれから - 教育とICT Online
西日本最大の教員養成大学である大阪教育大学は、「令和の日本型学校教育」を担う教員養成の在り方を変革するけん引役として、文部科学省から「教員養成フラッグシップ大学」の一つに選ばれている。総合教育企業のスプリックスは、個別指導塾の運営や教材開発などを通じて、付加価値の高い教育サービスを提供している。日本の教育に深く関わる両者が、情報教育と教員養成をテーマに座談会を実施し、次世代を見据えた教育改革における課題とその可能性について、多角的な視点から議論した。座談会の会場は、大阪教育大学天王寺キャンパスの産官学連携拠点「みらい教育共創館」。進行は、大阪教育大学客員教授で日経BP技術プロダクツユニット長補佐の中野淳が務めた。

【子どもの伸びしろを数値化】日本発 教育革命/世界44カ国が熱望するTOFASとは何か/SPRIX【&questions】
【Sponsored by スプリックス】 注目すべき企業やプロジェクトのトップランナーを招き、 キーワードをもとに掘り下げていく ...

ChatGPTは、プログラミングの常識をどう変えた?
これまで特別な技能だったプログラミングは誰もが通る基礎科目になった。はたして、AIと日常的な言葉で対話できる今、プログラミング言語は必要なのか。これから社会に出てくるプログラミング・ネイティブ世...

“普通の子”がトップ校に合格!子どものポテンシャルを引き出す3つのポイント
日本社会は子どもたちの可能性をまだまだ引き出し切れていない。 実際の教育現場を見ると、「勉強の楽しさに気づいていない」「自分の学力の可能性を見出せていない」「もっと上を目指す素質があるのに、イ...

ICT活用事例/山形県酒田市教育委員会 端末活用を促進するために「CBT for school」を導入 一人ひとりのペースで学びを積み重ね学習習慣と自発的な力を養う - 日経クロステック Special
2023年1月、教育DXを推進する山形県酒田市教育委員会は、1人1台端末の活用促進を目指して、株式会社スプリックスとの連携協定締結を発表。現在、市内のすべての小・中学校において、同社が開発した「CBT for school」を活用している。CBTを導入した目的は何か。なぜ、「CBT for school」を選んだのか。授業ではどう活用し、どのような教育効果を上げているのか。酒田市教育委員会の教育次長 佐藤 元氏に話を聞いた。

日経BP 教育関係者座談会「教育データとCBTの利活用による学びの深化」個別最適で協働的な学びを実現する、GIGAスクール構想の先にあるデータ活用 - 日経クロステック Special
GIGAスクール構想により児童・生徒1人1台のデジタル端末と高速の校内ネットワークの整備が進み、教育現場や教育委員会、教員養成系大学などで、教育データの利活用に対する関心が高まっている。文部科学省もデジタル技術とデータを活用して、知見の共有と新たな教育価値の創出を進める「教育DX(デジタル・トランスフォーメーション)」の方向性を提示。こうした流れを受けて日経BPでは、教育データとCBTの利活用について有識者が議論を交わす座談会を企画した。
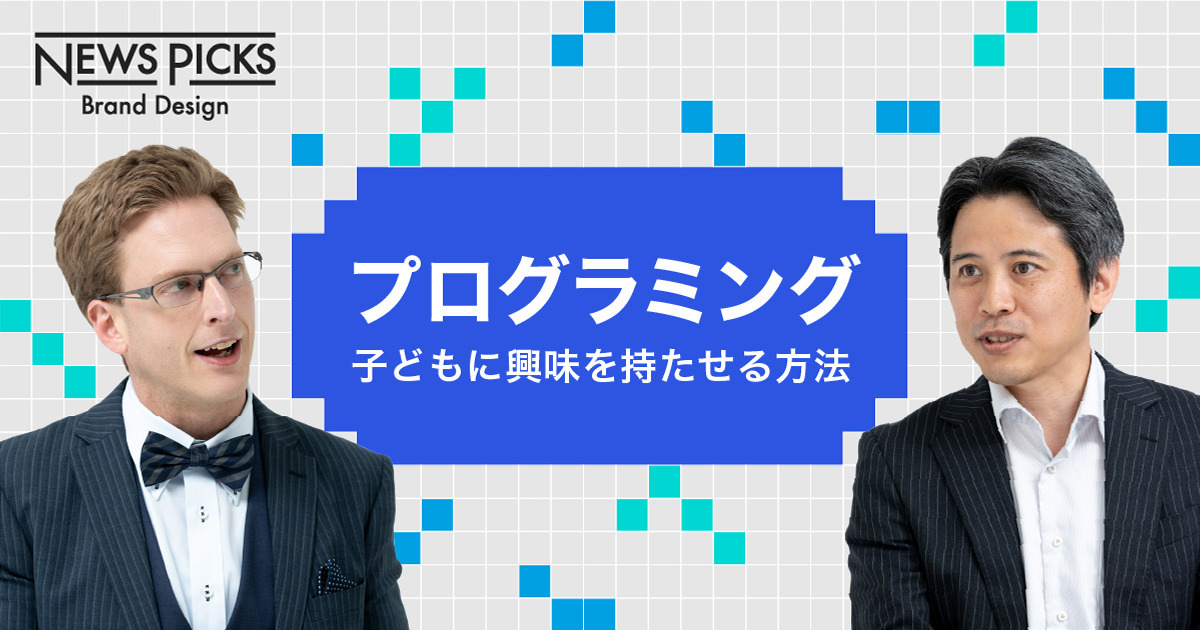
【必見】子どもにプログラミングを好きになってもらう方法
「取材の趣旨はわかりました。ところで……この“プログラミング”ってなんですか?」 打ち合わせ中、真顔でとぼけて周囲を困惑させたが、もちろんこの人が知らないわけがない。「Why!」でおなじみ厚切り...

【塾×AI】子どもの“自ら学ぶ力”を育む3つの仕掛け
──今の学びの場には、どんな課題がありますか?長濱 ここ10年の学習指導要領の改訂で、子どもたちが学校で学ぶ内容は、ゆとり教育と比べて幅が広がり、同時に量も増加していました。 その影響で授業の進...

【必修】子どもに学ぶ「自己肯定感」の高め方
学習塾業界では圧倒的な知名度を誇る「森塾」。サービスの品質にこだわりながら、直営展開で拡大を続け、今や関東を中心に190を超える教室を展開している。そんな「森塾」を運営するスプリックスの代表取締...

【必修】デジタルを動かす「プログラミング・ネイティブ」を育てる
小・中学校でのプログラミング教育が必修となり、子どもたちがプログラミングを学べるビジュアル言語やツールも増えている。今回取り上げるのは、ITベンチャー第一世代であるサイバーエージェントと基礎学力...

【学びを科学する】子どもたちは考える「基礎」をどう身につけるのか
問いを立てればAIやコンピューターが答えを出してくれる時代。ビジネスリテラシーとしても、課題発見などの「思考力」や「応用力」が重視されている。だが、思考のベースとなる「基礎学力」は、いつどのよう...

【塾×テクノロジー】EdTechの本質は、「人」だ。
──そら塾が始まったのは、コロナ禍第一波の2020年6月1日。約1年間で順調に生徒数を伸ばしているとのことですが、その理由をどう分析していますか。 コロナ禍による「対面の塾に行きたくない」という...